リサイクルマークは、毎日目にするペットボトルや食品のパッケージなどに必ずついている大切な印です。でも「このマークってどういう意味?」「数字や文字の違いは?」と疑問に思ったことはありませんか?この記事では、リサイクルマークの種類と意味を一覧でわかりやすく解説し、正しい分別や捨て方も紹介します。調べ学習や自由研究にも使える内容なので、ぜひ参考にしてください。
リサイクルマークとはどんなマーク?

リサイクルマークとは、入れ物や包みの材料を教えてくれたり、正しい仕分けのやり方を伝えたりするために付けられているマークです。日本では法律により、決まった入れ物や包みにマークを付けることになっています。これらのマークを見ることで、その製品がリサイクルできるかどうか、どのように仕分けすればよいかが一目でわかるようになっているのです。
リサイクルマークには大きく分けて3つの種類があります。「法律で付けることが決められているもの」、「会社が自分から付けているもの」、「そして地球にやさしい製品であることを表すもの」。マークを正しく覚えて適切にリサイクルすることで、資源を大切に使い、地球の環境を守ることにつながります。
リサイクルマークの意味を一覧でチェック!

リサイクルマークにはたくさんの種類があり、それぞれ違う意味を持っています。ここでは、毎日の生活でよく見かける主要なマークについて、その意味と使われている商品を表でわかりやすく紹介していきます。どのマークがどんな製品についているか確認してみましょう。

統一美化マーク
どんな意味?
ごみをポイ捨てしないでね!という意味
どんな商品についてる?
飲み物の容器の広告やパンフレット
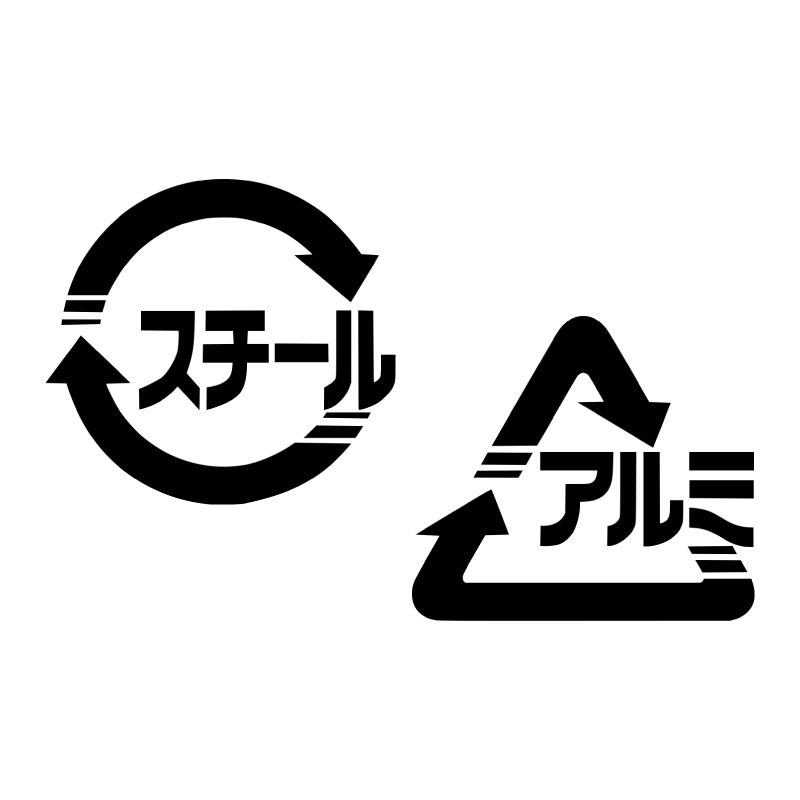
缶のマーク
どんな意味?
缶の材料を教えてくれるマーク
どんな商品についてる?
ジュース缶、コーヒー缶、ビール缶など

ペットボトルのマーク
どんな意味?
ペットボトルであることを示すマーク
どんな商品についてる?
飲み物のペットボトル、調味料のボトル
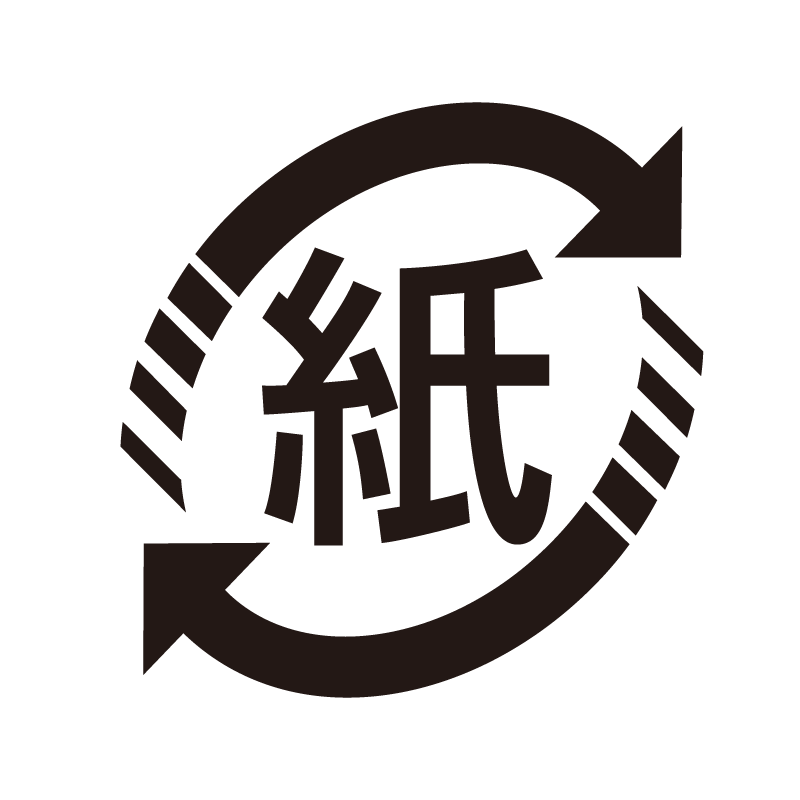
紙マーク
どんな意味?
紙でできた容器のマーク
どんな商品についてる?
お菓子の箱、冷凍食品の箱など

紙パックのマーク
どんな意味?
紙パックであることを示すマーク
どんな商品についてる?
牛乳パック、ジュースパック

プラスチック容器のマーク
どんな意味?
プラスチックでできた容器のマーク
どんな商品についてる?
お弁当の容器、カップめんの容器など

ダンボールのマーク
どんな意味?
ダンボールであることを示すマーク
どんな商品についてる?
宅配便の箱、商品の梱包箱

古紙を使った紙のマーク
どんな意味?
古い紙をリサイクルして作った紙のマーク
どんな商品についてる?
トイレットペーパー、ティッシュ

グリーンマーク
どんな意味?
リサイクルした紙で作られた商品のマーク
どんな商品についてる?
ノート、コピー用紙など

ペットボトルから
作られた商品のマーク
どんな意味?
ペットボトルをリサイクルして作った商品のマーク
どんな商品についてる?
洋服、バッグ、文房具など

牛乳パックから
作られた商品のマーク
どんな意味?
牛乳パックをリサイクルして作った商品のマーク
どんな商品についてる?
トイレットペーパー、ティッシュなど
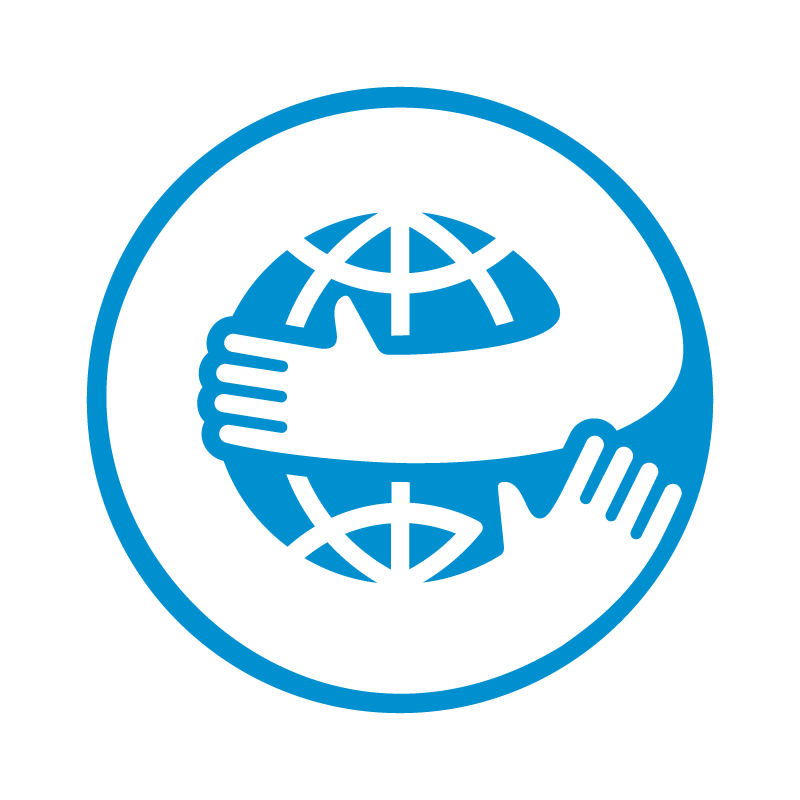
エコマーク
どんな意味?
地球にやさしい商品のマーク
どんな商品についてる?
環境に配慮した様々な商品

統一美化マーク
統一美化マークは、飲み物の入れ物をポイ捨てしないでリサイクルしましょうという意味を持つマークです。1981年に作られて、散らかすことを防いでリサイクルをすすめることが目的になっています。
このマークは法律で付けることが決められているわけではありませんが、テレビCMや新聞、雑誌の広告、お知らせのパンフレットなどに広く使われています。飲み物の入れ物を正しく捨てることの大切さを伝える代表的なマークとして、多くの人に親しまれているのです。
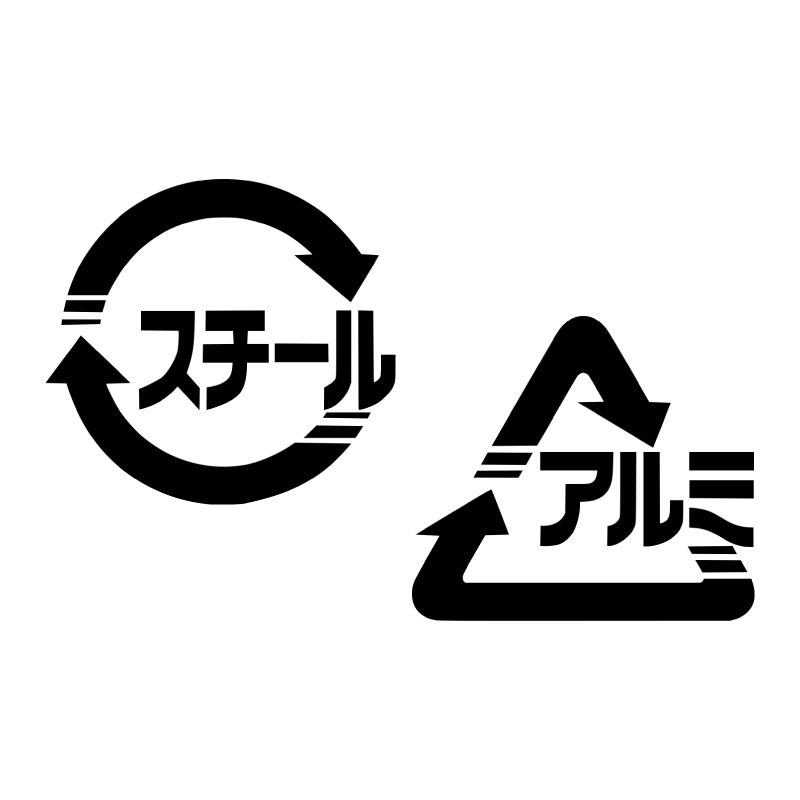
缶のマーク(アルミ缶・スチール缶)
缶のマークは、その缶がアルミでできているかスチールでできているかを教えてくれるマークです。アルミ缶は軽くてやわらかく、主にビールや炭酸飲料(ジュース)に使われています。
一方、スチール缶は強くて熱に強いため、缶コーヒーや緑茶の飲み物、果実の飲み物などに使われているという特徴があります。このマークは法律により付けることが決められていて、みんながアルミ缶とスチール缶を仕分けしやすくするために付けられているのです。

ペットボトルのマーク
ペットボトルのマークは、三角の形の中に「1」と書かれた形をしていて、PET(ペット)という材料でできていることを表しています。このマークは飲み物やお酒、しょうゆやドレッシングなどのペットボトルに付けることが決められているもの。
ペットボトルとそれ以外のプラスチックの入れ物を分けるために作られました。ペットボトルは他のプラスチックの入れ物とは違うやり方でリサイクルされるため、仕分けの時にはこのマークを確認することが大切になります。
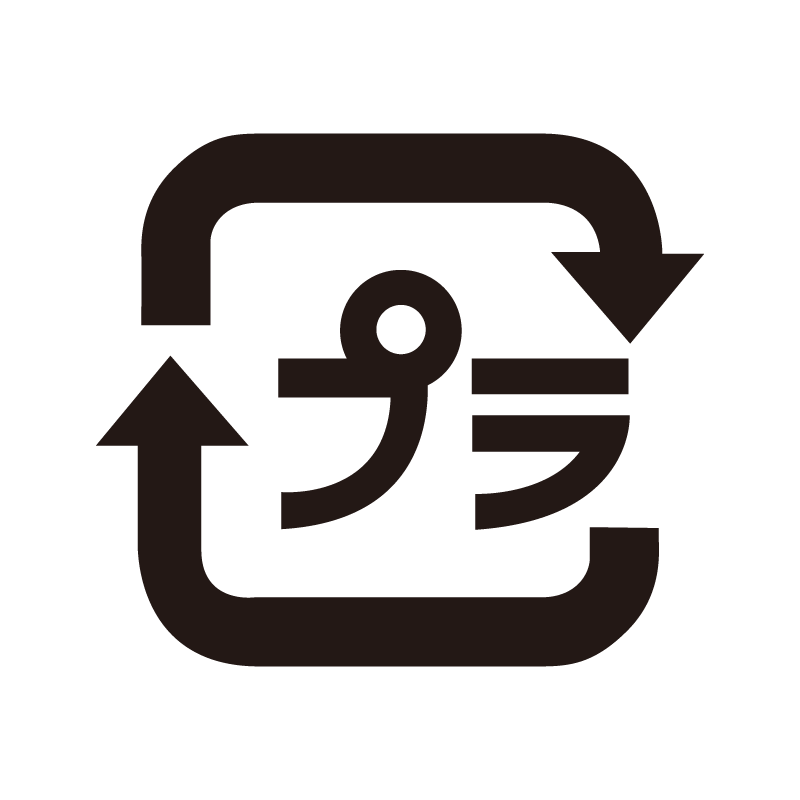
プラスチック容器のマーク
プラスチック入れ物のマークは、四角の形の中に「プラ」と書かれた形をしていて、ペットボトル以外のプラスチックでできた入れ物に付けられています。お弁当やカップめんの入れ物、ヨーグルトのカップ、化粧品のパッケージ、食品トレー、発泡スチロールなど、身近にある多くの商品に使われているマークです。
このマークが付いた入れ物は、プラスチック製容器包装として分別回収され、リサイクル資源として活用されています。
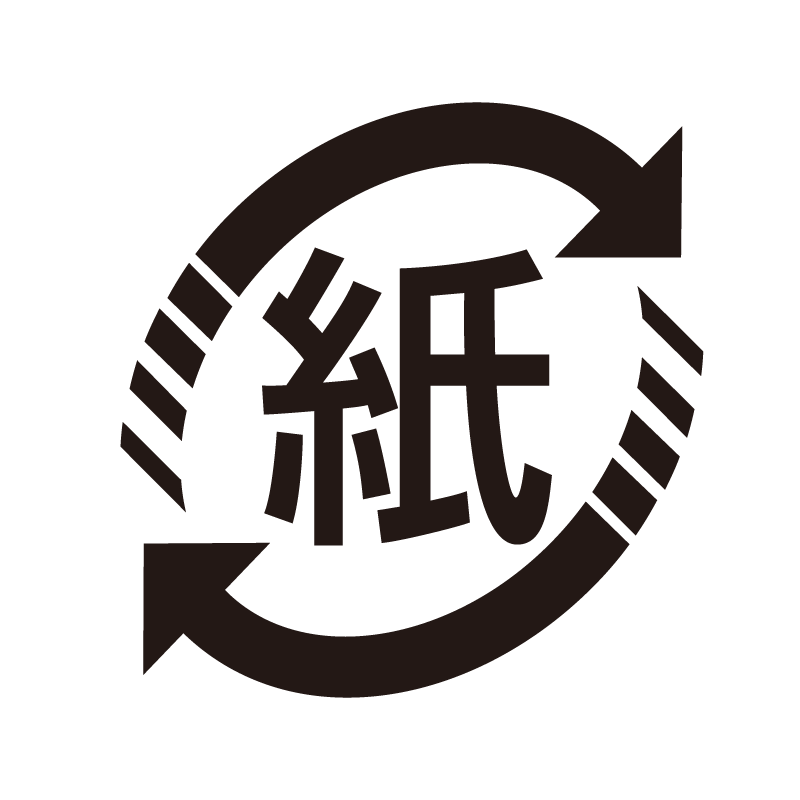
紙でできた容器のマーク(紙マーク)
紙でできた入れ物のマークは、紙製の入れ物や包みに付けられているマークで、波線のような形をしています。お菓子の箱や冷凍食品の箱、包装紙、紙袋などに表示されているもの。
ただし、飲み物用でアルミを使用していない紙の入れ物と段ボールは除かれます。このマークは法律により表示することが決められていて、紙製容器包装として適切にリサイクルするために重要な役割を果たしています。

紙パックのマーク
紙パックのマークは、牛乳パックやジュースパックなど、アルミを使用していない紙パックの入れ物に表示されているマークです。このマークは、リサイクルできる紙パックであることを表しています。
一方、内側にアルミを使用している紙パックは「禁忌品(きんきひん)」と呼ばれ、これはリサイクルの時に混ぜてはいけない品物という意味で、普通の紙と一緒にリサイクルに出すと工場でトラブルの原因となってしまいます。そのため、この紙パックのマークは、アルミなしの安全にリサイクルできる紙パックを見分けるために業界が自分から表示しているものです。

ダンボールのマーク
ダンボールのマークは、リサイクルできるダンボールに表示されているマークです。宅配便の箱や商品の梱包箱など、私たちの生活に欠かせないダンボールの製品に付けられています。
ダンボールは他の材料と比べて非常にリサイクルしやすく、実際に高い割合でリサイクルされている材料として知られています。このマークは業界が自分から表示しているものです。

古紙を使った紙のマーク
古い紙を使った紙のマークは、「Rマーク」とも呼ばれ、古い紙をリサイクルして作られた紙製品に表示されています。トイレットペーパーやティッシュペーパーなどの日用品によく見かけるマークです。
マークの右側には古い紙の配合率が%で表示されていて、どのくらいリサイクル材料が使われているかがわかります。1995年にごみを減らすための会議によって決められたもので、古い紙を再利用していることを表す重要な目印となっています。

グリーンマーク(再生紙のマーク)
グリーンマークは、決められた割合以上の古い紙が使用されている再生紙の製品に付けられるマークです。ノートやコピー用紙などによく表示されています。
古い紙の使用割合は基本として40%以上と決められていますが、トイレットペーパーやティッシュペーパーは100%、新聞用紙やコピー用紙は50%など、製品によって基準が違います。
公益財団法人古紙再生促進センターの許可を受けた製品にだけ付けられるマークで、環境に配慮した製品を選ぶときの目安になります。

ペットボトルから作られた商品のマーク
ペットボトルから作られた商品のマークは、使用済みペットボトルをリサイクルして作られた製品に表示されているマークです。洋服やバッグ、文房具など、私たちの身近な商品に使用されています。
PETボトルリサイクル推進協議会が決めたもので、リサイクル製品を多くの人に知ってもらい、買ってもらうことが目的です。このマークが付いた商品を選ぶことで、資源の循環利用に貢献できます。

牛乳パックから作られた商品のマーク
牛乳パックから作られた商品のマークは、使用済みの牛乳パックを原料にして作られた製品に表示されています。トイレットペーパーやティッシュペーパー、名刺、ハガキ、カレンダーなどの紙製品によく見かけるマークです。
全国牛乳パックの再利用を考える連絡会という市民の組織が牛乳パックの再利用をすすめるために作ったもので、牛乳パックリサイクルマークとも呼ばれています。
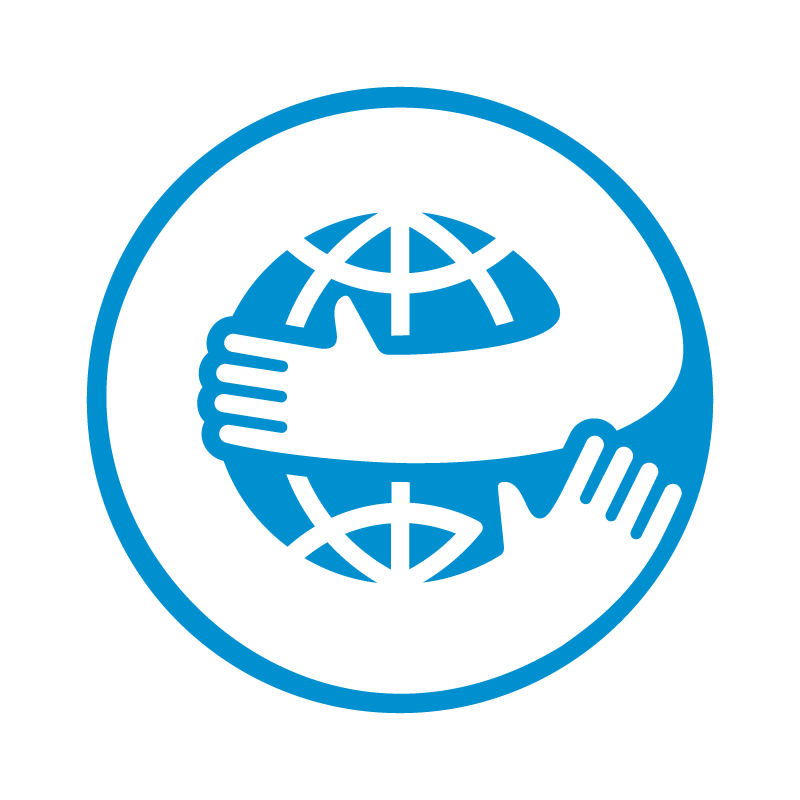
エコマーク
エコマークは、作るところから捨てるところまでのすべての段階で環境への負担が少なく、環境を守るのに役立つと認められた商品に付けられるマークです。ゴミ袋やタオル、石鹸、食器、パソコンなど、色々な製品に表示されています。
公益財団法人日本環境協会が運営していて、「資源を節約すること」「地球温暖化を防ぐこと」「有害な物質をコントロールすること」「生き物の多様性を守ること」という4つの項目を重点的に評価して認定。地球にやさしい商品を見分ける重要な目印となっています。
リサイクルマークの数字や文字の意味を知ろう

ペットボトルマークの三角の中にある「1」という数字は、アメリカのプラスチック産業協会が1989年に決めたSPIコードという分類方法に基づいています。
この番号のしくみでは、プラスチックの材料によって1から7までの数字が割り振られていて、1はPET樹脂、2は高密度ポリエチレン、3は塩化ビニル、4は低密度ポリエチレン、5はポリプロピレン、6はポリスチレン、7は複合材やその他を表しています。
日本でも以前はこのコードを使うことが推奨されていましたが、現在使用されているのは「1」だけで、飲み物やお酒、しょうゆ用の入れ物に表示されています。
「プラ」マークの下に書かれている文字の秘密
プラスチック製容器包装マークの四角の下に書かれている「PE」や「PP」などの文字は、その入れ物がどんなプラスチック材料でできているかを教えてくれる材質記号です。記号が1つだけ書かれている場合は単一材質といって、1つの材料だけで作られていることを意味します。
複数の記号が書かれている場合は複合材質といって、いくつかの材料を組み合わせて作られていて、最も多く使われている材料には下線が引かれています。この表示により、リサイクル時により適切な処理が可能になっているのです。

よく見る材質記号を覚えよう!
プラスチック製品によく見られる材質記号を覚えておくと、どんな材料でできているかがすぐにわかります。PPはポリプロピレンでお弁当箱や食品トレーに、PEはポリエチレンでレジ袋やボトルに、PSはポリスチレンでカップめんの入れ物や発泡スチロールに使われています。
PETはポリエチレンテレフタレートでペットボトルに、PVCはポリ塩化ビニルで包装フィルムに使用されているもの。また、EVOHはエチレン-ビニルアルコール樹脂、Pは紙、Mは金属(スチール、アルミなど)を表す記号として使われています。
「キャップ」や「ボトル」の表示って何?
プラスチック製容器包装マークの下に「キャップ:PE」や「ボトル:PP」と書かれているのを見たことがありませんか。これは「役割名」といって、その入れ物のどの部分がどんな材料でできているかを詳しく教えてくれる表示です。
1つの製品でもパーツごとに違う材料が使われていることが多く、「外箱」「フタ」「中袋」「個包装」「仕切り」などの役割名が表示されています。この表示があることで、仕分けの時にどの部分をどのように処理すればよいかがわかりやすくなり、より効果的なリサイクルが可能になっているのです。
リサイクルマーク別の正しい捨て方

リサイクルマークがついた製品は、マークの種類によって捨て方が全く違います。間違った仕分けをしてしまうと、せっかくリサイクルできる資源が無駄になってしまうことも。
ここでは主要なリサイクルマークごとに、正しい処分方法を手順を追って詳しく説明していきます。お住まいの地域によってルールが違う場合もあるので、市区町村の仕分け方法も併せて確認しましょう。
缶のマーク(アルミ缶・スチール缶)
缶のマークがついた製品は、以下の手順で処分しましょう。
- 缶の中身を完全に使い切る
- 水で軽くすすぎ洗いして汚れを落とす
- アルミ缶とスチール缶を仕分けする(マークを確認)
- 決められた缶類の回収日に出す。
アルミ缶は磁石にくっつかず、スチール缶は磁石にくっつくという特徴もあるので、マークが見にくい時は磁石で確認することもできます。つぶしても構いませんが、市区町村によってはつぶさずに出すよう決めている場合もあります。
ペットボトルマーク
ペットボトルマークがついた製品の処分手順は次の通りです。
- 中身を完全に使い切る
- キャップとラベルを取り外す
- 入れ物を水で軽くすすぎ洗いする
- キャップ、ラベル、ボトルをそれぞれ決められた仕分け方法で出す。
キャップとラベルはプラスチック製容器包装として、ボトル本体はペットボトルとして仕分けするのが一般的。ボトルは軽くつぶして小さくしても問題ありませんが、キャップは必ず取り外すことが重要です。
プラスチック容器マーク
プラスチック入れ物マークがついた製品は、以下の方法で処分します。
- 入れ物の中身や汚れを取り除く
- 水で軽く洗って汚れを落とす
- 乾かしてから「プラスチック製容器包装」として決められた日に出す
- 汚れが落ちにくいものは燃えるごみとして処分する場合もある。
- 発泡スチロールやマヨネーズの入れ物など、水で洗っても汚れが落ちにくいものは、市区町村によって処分方法が違うため確認が必要。基本的にはきれいな状態にしてからリサイクルに出すことが大切です。
紙でできた容器マーク
紙でできた入れ物マークがついた製品の処分方法は次の通りです。
- 中身を完全に取り出す
- 紙以外の部分(プラスチック窓やテープなど)をできるだけ取り除く
- 汚れがひどくない場合は「資源ごみ」や「古紙・資源」として出す
- 油汚れなどがひどい場合は燃えるごみとして処分する。
お菓子の箱や冷凍食品の箱などは比較的きれいなのでリサイクルしやすいのですが、宅配ピザの箱など油汚れがついたものは燃えるごみになることが多いです。
紙パックマーク
紙パックマークがついた製品は、以下の手順で処分してください。
- 中身を完全に使い切る
- 水で軽くすすぎ洗いする
- はさみで切り開いて平らにする
- よく乾かしてから「資源ごみ」や、「紙パック類」として決められた回収場所に出す。
スーパーや学校などに専用の回収ボックスが設置されていることも多いので、利用してみましょう。内側にアルミが貼ってある紙パックは仕分け方法が違う場合があるため、マークをよく確認することが重要になります。
ダンボールマーク
ダンボールマークがついた製品の処分方法は次の通りです。
- 中身をすべて取り出す
- ガムテープや宅配伝票などを取り除く
- 折りたたんで平らにする
- 「古紙類」または「ダンボール類」として決められた回収日に出す
- 雨に濡れないよう注意する。
大きなダンボールは適当なサイズに切って束ねることが必要な場合もあります。濡れてしまったダンボールはリサイクルできないため、回収日の天気にも注意しましょう。
マークがない容器の捨て方はどうする?
リサイクルマークがついていない入れ物は、基本的に燃えるごみまたは燃えないごみとして処分することになります。プラスチック製のものでも、マークがなければ一般的にはリサイクル対象外となるため注意が必要です。
ただし、市区町村によっては独自のルールを設けている場合もあるので、お住まいの地域の仕分け方法を確認してください。マークがない理由として、容器包装リサイクル法の対象外である場合や、表示義務のない小さなサイズである場合などが考えられます。迷った時は市区町村の窓口に問い合わせることをおすすめします。
ペットボトルキャップが生まれ変わる!ミタニの「ミクスチャーサイクル」

リサイクルマークを正しく理解して適切に仕分けることで、資源を大切に使い環境を守ることができます。会社でも色々なリサイクル技術が開発されていて、株式会社三谷バルブの「ミクスチャーサイクル」もその一つ。
この技術では、ペットボトルキャップ約2000個(約5キロ)を細かく砕いて、オリジナルのブレンド材を加えることで、新品と同じくらいの品質を持つエアゾール製品のキャップやボタンに生まれ変わらせています。
このように、私たちが正しく仕分けしたリサイクル資源は、新しい製品として再び私たちの生活に戻ってきます。ミクスチャーサイクルでは、新たにプラスチックを作る必要がないためCO₂を減らすことにも貢献でき、コストを下げることと環境への配慮を両立。一人ひとりの小さな行動が、大きな環境保護につながっていることを実感できる素晴らしい例といえます。
– 関連記事 –


