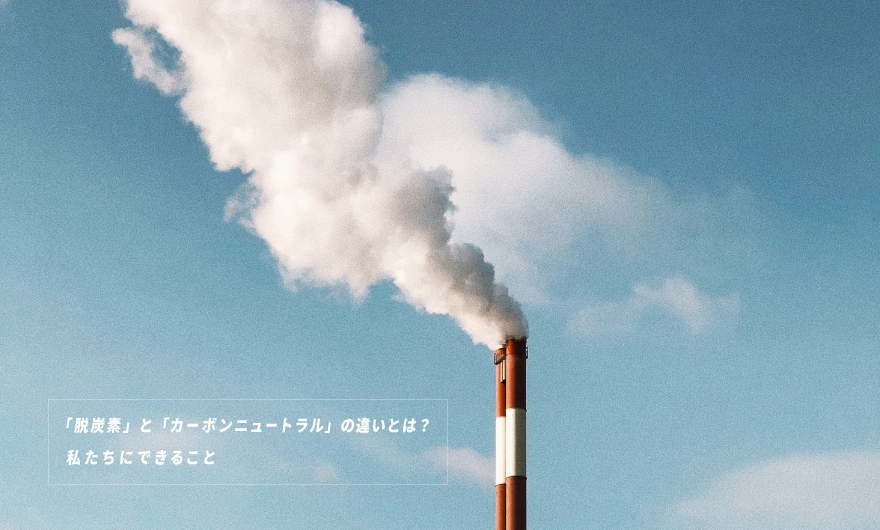地球温暖化対策が世界中で大切になっている今、「脱炭素」や「カーボンニュートラル」という言葉をよく耳にします。この2つの言葉は似ているように感じますが、実は意味が違います。この記事では、脱炭素とカーボンニュートラルの違いをわかりやすく説明し、地球環境を守るためにどんな取り組みが行われているのかを紹介します。企業や私たち一人ひとりができる環境にやさしい活動について知りたい方に役立つ情報をお伝えします。
脱炭素とカーボンニュートラルの違い

地球温暖化を防ぐために大切な2つの考え方「脱炭素」と「カーボンニュートラル」。どちらも二酸化炭素(CO2)を減らす取り組みですが、その方法には違いがあります。「脱炭素」はCO2を出さないようにすることを目指す考え方です。
一方、「カーボンニュートラル」は出してしまったCO2と同じ量を木を植えるなどして吸収し、全体としてプラスマイナスゼロにする考え方です。
| 項目 | 脱炭素 | カーボンニュートラル |
|---|---|---|
| 意味 | CO2の排出を減らしてゼロに近づける | CO2を出しても、同じ量を吸収してプラスマイナスゼロにする |
| 対象となるもの | 主にCO2 | 7種類の温室効果ガス全般 |
| 目指す状態 | 排出量そのものをゼロにする | 排出量と吸収量のバランスをとる |
| 主な取り組み | 化石燃料をやめる、省エネする | 森林を増やす、CO2を回収する技術の開発 |
このように目標は同じでも、取り組み方が異なる2つの考え方について詳しく見ていきましょう。
脱炭素とは
脱炭素とは、CO2を出さない社会を目指すことです。日本政府は2020年に「2050年までに脱炭素社会を実現する」と宣言しました。脱炭素という言葉に正確な決まりはありませんが、普通は「CO2の排出をできるだけ減らしてゼロに近づける」という意味で使われています。
なぜCO2を減らす必要があるのでしょうか。CO2は地球温暖化の主な原因となる気体の一つで、増えすぎると気候変動が起こるからです。脱炭素の取り組みでは、石油や石炭などの燃料を使わないようにしたり、電気やガスの使用量を減らしたりするなど、CO2を出さないことに力を入れています。
カーボンニュートラルとは
カーボンニュートラルとは、出すCO2と吸収するCO2の量を同じにして、実質ゼロにすることです。環境省の説明では「温室効果ガスの排出量と吸収量のバランスをとる」ということです。
仕事や日常生活でどうしても出てしまうCO2を、森や植物による吸収や技術的な回収などで同じ量だけ減らし、全体として排出量をゼロにする考え方なのです。
カーボンニュートラルは、CO2だけでなく、メタンやフロンガスなど地球温暖化の原因となる様々な気体も対象にしています。森林での光合成や木を植える活動、またはCO2を回収して地中に埋める技術など、いろいろな方法で温室効果ガスの吸収・除去に取り組み、出す量と吸収する量のバランスをとるのがカーボンニュートラルの考え方です。
脱炭素社会へ向けた取り組み

世界や日本では「脱炭素社会」を実現するために、様々な取り組みが進められています。脱炭素社会とは、温室効果ガスを出さない社会のことで、2015年に結ばれたパリ協定以降、世界共通の目標になっています。
実現には、温室効果ガスを減らすだけでなく、出された気体を吸収・除去する取り組みも必要です。国や企業、そして私たち一人ひとりができる脱炭素への取り組みについて見ていきましょう。
再生可能エネルギーの活用
再生可能エネルギーとは、太陽の光や風の力など自然界にあるエネルギーを利用した発電方法です。使っても無くならず、何度でも使えるエネルギー源のことを言います。
これらは発電するときにCO2を出さないため、脱炭素社会の実現に大きく役立ちます。太陽光発電は家庭でも取り入れやすく、風力発電はコストが安いなど、それぞれに特徴があります。
工場でも太陽光パネルの設置が進んでいます。三谷バルブでは、工場に太陽光発電の設備を導入しており、工場で使う電気によるCO2の量を年間約10%減らす取り組みを行なっています。
家庭でも太陽光パネルを付ければ電気代を節約できるだけでなく、余った電気を売ることもでき、お金の面でもお得です。
省エネ設備の導入
省エネ設備とは、少ないエネルギーで効率よく動く機械や設備のことです。同じ効果を得るために使うエネルギーを減らすことができます。
例えば、LED電球は昔の白熱電球と比べて使う電気の量が約1/5〜1/7と言われており、電気代の節約だけでなくCO2を減らすことにも役立ちます。
家や会社でできる省エネの例として、エアコンの使用時間を1日1時間減らすと年間で約26kgのCO2削減になるという効果があります。また、省エネ型の給湯器に替えたり、家の断熱性を高めたりするリフォームなども省エネに効果的です。
省エネは環境に良いだけでなく、電気代やガス代などの光熱費も減るため、経済的にもメリットが大きいのです。
カーボンオフセットとJ-クレジット制度の活用
カーボンオフセットとは、自分が出したCO2を、別の方法で埋め合わせることです。例えば、飛行機に乗るとCO2が出ますが、その分の排出量を相殺するために森林保護活動にお金を寄付するなどの取り組みがカーボンオフセットにあたります。
J-クレジットとは、CO2を減らした分を「権利」として売り買いできる仕組みのことです。例えば、会社が省エネ設備を導入してCO2排出量を減らした場合、その減らした量を「クレジット」として国が認め、他の会社に売ることができます。
買った会社はそのクレジットを使って、自社のCO2排出量を相殺できるのです。この制度によって、環境への取り組みがお金になり、社会全体での脱炭素化が進むようになっています。
カーボンリサイクル技術の開発と実用化
カーボンリサイクルとは、出てしまったCO2を集めて再利用する技術のことです。CO2は今まで「邪魔なもの」と思われてきましたが、この技術により「役立つもの」として活用できるようになります。
例えば、CO2からプラスチックを作る技術や、コンクリートにCO2を閉じ込める技術などが開発されています。
日本はこの分野で世界の先頭に立つため、2019年に「カーボンリサイクル技術ロードマップ」という計画を作り、2021年に改訂しました。この計画では、2030年までを第1段階、2040年までを第2段階、それ以降を第3段階として、少しずつ技術開発と普及を進めることになっています。
現在、コンクリートや化学品の一部で実際に使われ始めており、将来的には多くの産業でCO2が資源として活用される可能性があります。
サプライチェーン全体でのCO2排出量の可視化と削減
サプライチェーンとは、商品が作られてから私たちの手元に届くまでの流れ全体のことです。商品の原料集めから製造、運搬、販売、使用、捨てるまでの各段階でCO2が出ており、企業が環境への負担を減らすためには、このサプライチェーン全体での排出量を把握し削減することが重要になっています。
CO2の「見える化」により、どの工程で多くの排出があるのかを特定し、効率的に減らす方法を考えることができます。例えば、食品の産地を近くのものにすると運搬時のCO2が減りますし、包装材を減らすことでも排出量を削減できます。
私たち消費者も、環境に配慮した商品を選ぶことで、間接的にCO2排出量の削減に協力することができるのです。
脱炭素・カーボンニュートラルと混同されやすい関連語句

脱炭素やカーボンニュートル以外にも、環境問題に関連する似た言葉がいくつかあります。特に注目すべき3つの言葉として、「RE100」「ゼロカーボン」「カーボンフリー」について説明します。
これらの言葉は国際的な取り組みや目標を表す大切な考え方であり、それぞれ少しずつ意味や重点が異なります。環境問題についての話し合いや情報を正しく理解するためにも、これらの言葉の違いを知っておくことは大切です。
RE100
RE100とは「Renewable Energy 100%(再生可能エネルギー100%)」の略で、企業が仕事で使う電力を100%再生可能エネルギーでまかなうことを目指す国際的な取り組みです。イギリスの非営利団体「The Climate Group」が始め、世界中に広がりました。
2021年時点で、世界25カ国から340社以上が参加しており、日本からは60社以上が加わっています。参加している企業の多くは世界的に有名な企業であり、環境問題への配慮が企業のイメージや消費者からの評価に直接影響することを理解しているのです。
RE100に参加するメリットとしては、企業イメージが良くなるだけでなく、長い目で見たエネルギーコスト削減や株主からの評価向上なども挙げられます。
ゼロカーボン
ゼロカーボンとは、CO2の排出量を全体として実質ゼロにすることを意味し、カーボンニュートラルと同じ意味で使われることが多い考え方です。世界各地の自治体では「ゼロカーボンシティ」を宣言し、地域レベルでの温室効果ガス排出量削減に取り組んでいます。日本でも2021年時点で444の自治体がゼロカーボンシティを宣言しています。
ゼロカーボンシティでは、太陽光発電の推進や電気バスの導入など、具体的な取り組みが行われています。海外では「ネットゼロ」という言葉も使われており、これも「CO2の排出と吸収をバランスさせて、差し引きゼロにする考え方」を意味しています。
カーボンフリー
カーボンフリーとは、CO2を出さない、または出さないように作られた製品やサービスのことです。カーボンフリーはカーボンニュートラルよりも厳しい考え方で、排出量そのものをゼロにすることを目指しています。
具体的な例としては、太陽光や風力などの再生可能エネルギーで発電された「カーボンフリー電力」や、CO2を出さずに作られた「カーボンフリー水素」などがあります。 カーボンフリーの達成はとても難しい目標ですが、環境問題に積極的な企業にとっては重要な目標となっています。
三谷バルブは脱炭素社会を目指します
三谷バルブは、エアゾールバルブやディスペンサーポンプのメーカーとして、環境に優しいモノづくりを目指しています。再生可能エネルギーを活用するため、茨城工場と白河工場に太陽光発電システムを導入し、工場での消費電力によるCO2排出量を年間10%(約65トン)削減する目標を掲げました。
また社用車を電気自動車に切り替えるなど、事業活動全体での環境負荷低減にも積極的に取り組んでいます。
製品開発においても、植物由来樹脂「グリーンポリエチレン」を使用したディスペンサーポンプ「Z-1000-C」や、従来品と比べて最大90%以上のCO2削減を実現したエアゾールバルブ「SWAYK」など、環境配慮型製品の開発を進めてきました。
三谷バルブは製品設計から製造、廃棄に至るまでのライフサイクル全体で環境に配慮した事業活動を展開しています。私たちの小さな一歩が、持続可能な社会の実現につながると信じて、これからも脱炭素社会に向けた取り組みを続けていきます。