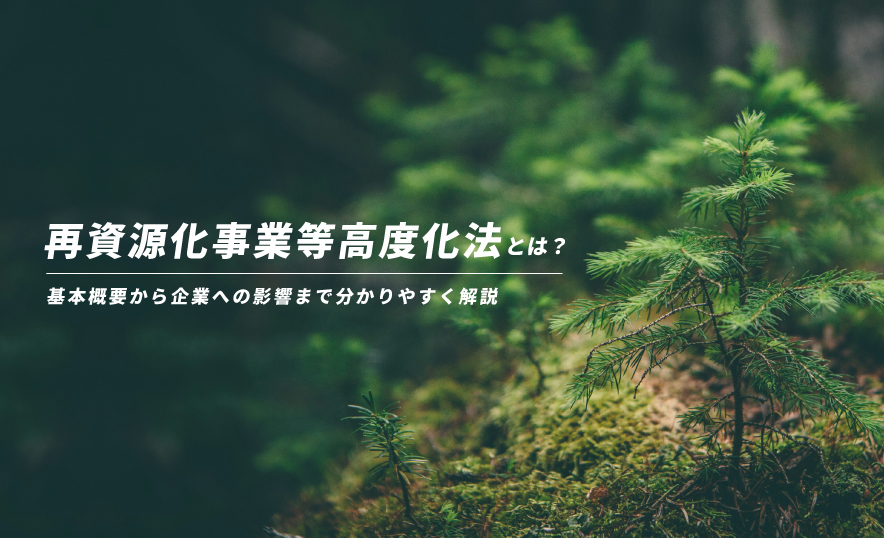2024年5月に始まった「再資源化事業等高度化法」という法律を知っていますか?この新しい法律は、日本のリサイクルを大きく変える可能性があります。製造業で働く方やサステナビリティに関わる方が押さえておきたい重要なポイントを、分かりやすくお伝えします。
再資源化事業等高度化法とは?

日本のリサイクルが大きく変わろうとしています。2024年5月に公布された「再資源化事業等高度化法」は、これまでのリサイクルをもっと効率的で環境に優しいものにするための法律です。
まずは、この法律の基本的な内容と、いつから始まるのかを確認してみましょう。
法律の正式名称と目的
正式な名前は「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」です。とても長い名前なので、普通は「再資源化事業等高度化法」と呼ばれています。2024年5月29日に公布されました。
この法律が目指していることは4つあります。
再資源化事業等高度化法の主な目的
・製造業者が必要とする質と量の再生材の確保
・資源循環産業の発展
・温室効果ガス排出量の削減
・産業競争力の強化
つまり、環境を守りながら、日本の産業も強くしようという法律なのです。
参照:環境省「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律について」
「再資源化」と「高度化」の意味
「再資源化」とは、使い終わった製品や材料を新しい製品の材料として再び使えるようにすることです。循環型社会形成推進基本法では、まず再使用を優先し、次に再生利用、それができない場合は熱回収を行うとされています。
「高度化」とは、温室効果ガスの排出削減効果を大きくすることを意味しています。つまり、従来のリサイクル方法よりも環境に優しい方法で再資源化を行うことが求められています。
廃棄物発電のような直接的な熱回収は、この法律の「再資源化」には含まれていません。
再資源化事業等高度化法の施行スケジュール
この法律は段階的に施行されます。いつからどの部分が始まるのかを確認しておきましょう。
| 施行時期 | 施行内容 | 主な規定 |
|---|---|---|
| 令和7年2月1日 | 一部先行施行 | 基本方針、特定産業廃棄物処分業者の条件、判断基準 |
| 令和7年11月まで | 本格施行 | 3つの認定制度、報告制度の本格運用 |
令和7年2月1日に一部の規定が先行して始まり、11月までに全ての制度が本格的にスタートします。
プラスチック資源循環促進法との違い

既に施行されているプラスチック資源循環促進法と、新しい再資源化事業等高度化法にはどのような違いがあるのでしょうか。対象範囲、規制の厳しさ、事業者への要求の3つの観点から比較してみましょう。
| 項目 | 再資源化事業等高度化法 | プラスチック資源循環促進法 |
|---|---|---|
| 対象 | 幅広い資源 | プラスチック製品全般 |
| 目的 | 資源循環産業全体の発展 | プラスチック廃棄物削減、リサイクル促進 |
| 特徴 | 高度な再資源化技術の導入支援 | 自主回収・再資源化事業計画の認定 |
| 重点 | 技術開発、再生材の質と量確保 | 回収、リサイクル、分別排出 |
プラスチック資源循環促進法、知っていますか?
プラスチック資源循環促進法は、2021年6月4日に国会で成立した法律です。深刻化する海洋プラスチックごみ問題や気候変動問題などへの対応を目的としたもので、プラスチック製品の設計から廃棄物処理までに関わるあらゆる自治体や事業者が対象になっています。
対象範囲の違い:プラスチックから全産業廃棄物へ拡大
プラスチック資源循環促進法は、その名前の通りプラスチック製品だけを対象としています。一方、再資源化事業等高度化法は、プラスチックに限らず全ての産業廃棄物を対象としています。
金属、ガラス、繊維など、様々な材料のリサイクルが含まれるため、より幅広い産業に影響を与える法律となっています。この拡大により、企業はより包括的な資源循環戦略を考える必要があります。
規制の厳しさの違い:自主的取り組みから報告義務・命令措置へ
プラスチック資源循環促進法では、主に事業者の自主的な取り組みを促進する内容でした。
しかし、再資源化事業等高度化法では、特定の廃棄物処理業者に対して報告義務を課し、基準を満たさない場合には国が指導、勧告、命令を行える仕組みになっています。つまり、より厳格な管理体制が導入されることになります。
事業者への要求レベルの違い:3R+Renewableから高度化・効率化へ
プラスチック資源循環促進法では「3R+Renewable」(削減・再利用・リサイクル・再生可能資源への転換)が基本的な考え方でした。再資源化事業等高度化法では、これに加えて「高度化・効率化」が求められています。
単にリサイクルするだけでなく、より高い技術を使って効率的に、そして環境負荷を減らしながら再資源化することが重要になっています。
再資源化事業等高度化法ができた背景・理由

なぜこの新しい法律が必要になったのでしょうか。その背景には、国際的な環境規制の強化、日本の循環型社会への取り組み強化、高品質なリサイクル材料の安定供給という3つの大きな理由があります。
海外の厳しい環境ルールに追いつく
2023年7月、欧州委員会は新しい規制案を発表しました。この規制では、新車を製造する際にリサイクル材を一定割合使用することが義務付けられています。具体的には、プラスチック部品の25%をリサイクル材で作らなければならないとされています。
このELV規則案(使用済み自動車に関する規則案)により、日本企業が欧州に輸出する製品も同様の基準を満たす必要が出てきました。このため、日本でも高品質なリサイクル材を安定的に供給できる仕組みを作ることが急務となったのです。
日本の循環型社会への取り組みを強化する
日本政府は2024年8月に発表した第五次循環型社会形成推進基本計画で、「循環経済への移行」を国の重要戦略として位置づけました。循環経済とは、廃棄物を出さずに資源を回し続ける経済の仕組みのことです。
この取り組みによって、環境問題の解決と経済成長を同時に実現し、地方の活性化や資源の安定確保も目指しています。
高品質なリサイクル材料を安定供給する
製造業からのリサイクル材への需要は高まっていますが、供給が追いついていません。特に以下のような課題があります。

太陽光パネルの大量廃棄問題
2012年頃から大量に設置された太陽光パネルが、25~30年の寿命を迎えて今後一斉に廃棄される予定
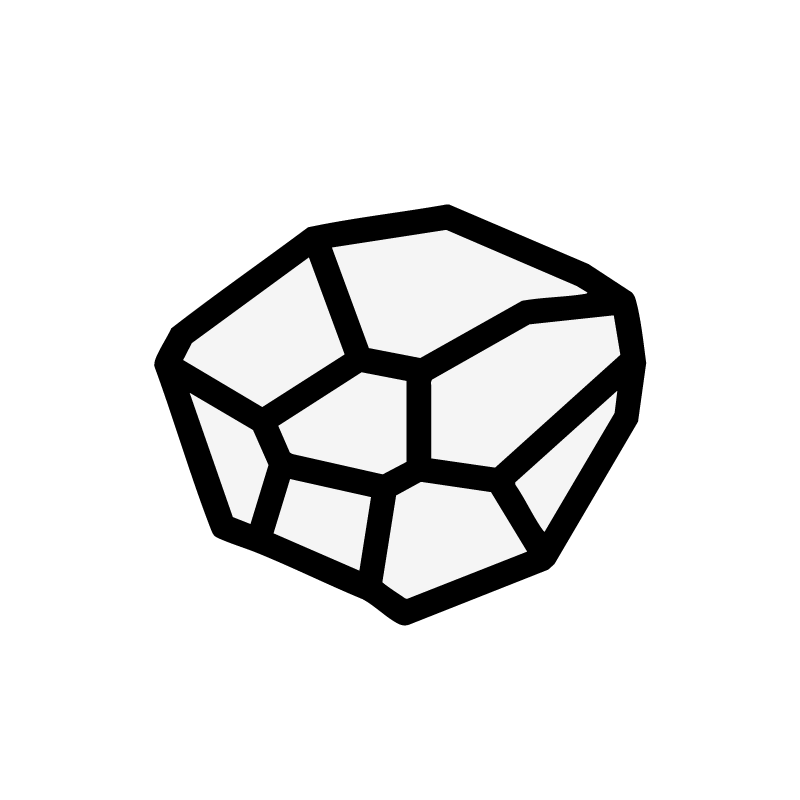
重要な鉱物の確保
レアメタルなど、日本が輸入に頼っている重要な資源の安定確保

石油依存からの脱却
石油由来の材料から、リサイクル材への転換
これらの課題を解決するためにも、この法律が作られました。
2025年11月の施行で製造業・事業者に起こる変化と対策
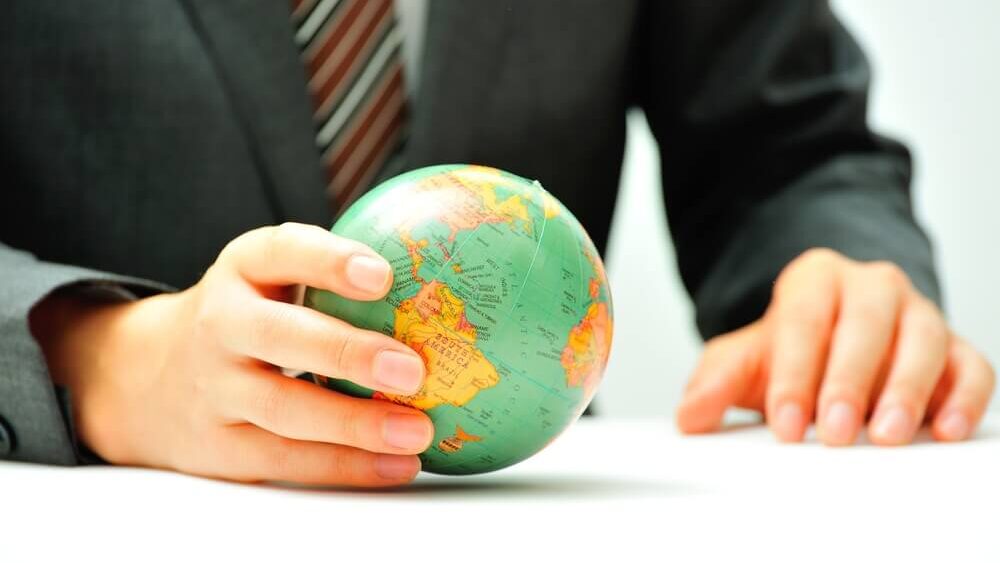
2025年11月までに本格施行される再資源化事業等高度化法により、製造業や事業者を取り巻く環境は大きく変わります。特に重要なのは、廃棄物処理を委託している業者への規制強化、高品質なリサイクル材の供給改善、そして認定制度による新たな競争環境の出現です。
これらの変化は一見すると廃棄物処理業界だけの問題に思えるかもしれませんが、実際には製造業や一般事業者の日常業務に直接影響を与えます。早めに対策を立てることで、変化を機会として活用できるでしょう。
廃棄物処理委託先の見直しが急務に
11月の施行により、大手廃棄物処理業者(年間10,000トン以上または廃プラスチック1,500トン以上を処理する業者)は「特定産業廃棄物処分業者」として指定され、毎年国への報告義務を負うことになります。
報告内容は、処分を行った廃棄物の数量と、そのうちどれだけを再資源化したかです。国が定めた基準を満たさない処理業者には、指導→勧告→命令という段階的な措置が取られ、最終的には命令違反で罰則を受ける可能性もあります。
これまで価格の安さだけで処理業者を選んでいた企業は、委託先の見直しを迫られます。基準を満たせない処理業者は市場から淘汰される可能性があり、委託先が突然事業停止するリスクも考えられます。
対策としては以下の点が重要です。
・委託先のリサイクル率や再資源化の取り組み実績を詳しく調査する
・処理方法の明確化、リサイクル率の最低保証などを契約に盛り込む
・リスク分散のため、基準を満たす複数の処理業者と契約を結ぶ
・11月施行前に信頼できる業者への切り替えを完了させる
リサイクル材の調達環境が大きく改善
認定制度の導入により、これまで課題だった高品質リサイクル材の安定供給が大幅に改善される見込みです。認定を受けた事業者は全国規模で事業展開でき、統一された高い基準でリサイクル材を製造できるようになります。
これまでリサイクル材は、品質のばらつきが大きく、必要な時に必要な量を確保することが困難でした。また、地域ごとに異なる基準で製造されるため、製品に使用する際の品質管理も複雑でした。
高品質で安定したリサイクル材の供給により、製品設計の自由度が大幅に向上します。また、欧州などの厳しい環境規制にも対応しやすくなり、輸出競争力の強化につながります。
対策としては以下の点が重要です。
・認定事業者からの調達を優先し、長期契約でリサイクル材を安定確保する
・リサイクル材の特性を活かした製品設計に変更し、環境配慮製品としてアピールする
・早期から認定事業者との関係を構築し、優先的な供給を受けられる体制を作る
・初期は価格が上昇する可能性があるため、段階的な導入計画を策定する
認定制度を活用した新規参入企業との競争激化
認定制度により廃棄物処理法の許可が不要になることで、これまで参入が困難だった企業も市場に参入しやすくなります。特に、高度な技術を持つ企業や全国展開力のある企業の参入が予想されます。
新規参入企業の特徴として、太陽光パネルの100%リサイクルや複合材料の高精度分離技術など高度な技術力を持つこと、認定により全国規模での事業が可能になるためスケールメリットを活かせること、税制優遇(35%特別償却)を活用した大規模な設備投資が可能なことが挙げられます。
従来の競合企業だけでなく、異業種からの参入により競争が激化します。環境配慮への取り組みが企業評価の重要な要素となり、対応の遅れは競争劣位に直結する可能性があります。
対策としては以下の点が重要です。
・3つの認定制度のうち、自社に適用可能なものがないか検討する
・リサイクル材使用製品や省エネ製品の開発を加速する
・競合他社に先駆けて環境対応を進め、ブランド価値を向上させる
・認定事業者との戦略的提携により、競争力を強化する
これらの変化を機会として捉え、積極的な対応を進めることが重要です。
再資源化事業等高度化法の詳しい概要

この法律では、「国」「廃棄物処理業者」「その他の事業者」それぞれの役割が明確に定められています。どのような内容になっているのか見てみましょう。
国がリサイクルの基本的な方向性を決める
環境大臣が、日本全体のリサイクルの方向性を決める「基本方針」を作ります。この基本方針には以下のような内容が含まれます。
・再資源化事業の効率的実施方法
・生産性向上策
・温室効果ガス削減措置
・再資源化目標の設定
国が明確な方向性を示すことで、全国の事業者が同じ目標に向かって取り組めるようになります。また、技術面でのサポートや、リサイクル材の需要と供給をつなぐ仕組み作りも国の重要な責務とされています。
ゴミ処理・リサイクル会社の新しい責務
ゴミ処理業者には、従来よりも厳格な責任が課せられます。特に処分量の多い業者は「特定産業廃棄物処分業者」として指定され、新たな報告義務や基準遵守が求められるようになります。
特定産業廃棄物処分業者の報告義務
特定産業廃棄物処分業者とは、年間の産業廃棄物処分量が10,000t以上、または廃プラスチック類の処分量が1,500t以上の事業者のことです。これらの事業者は、毎年度、処分を行った数量と再資源化した数量を国に報告しなければなりません。
| 廃棄物の種類 | 年間処分量の基準 |
|---|---|
| 産業廃棄物全般 | 10,000t以上 |
| 廃プラスチック類 | 1,500t以上 |
この報告制度により、国は全体的な再資源化の状況を把握し、より効果的な政策を策定できるようになります。
参照:環境省「廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項について定める省令案 概要」
基準に達しない場合の指導・勧告・命令
国が定めた判断基準と照らし合わせて、再資源化の実施状況が著しく不十分だと判断された場合には、段階的な措置が取られます。
まず指導が行われ、改善されない場合は勧告、それでも改善されない場合は命令が出されます。命令に違反した場合には罰則も設けられています。
各事業者が自主的に取り組むべきこと
法律では、以下のような関係者それぞれの努力義務も定められています。
| 主体 | 責務内容 |
|---|---|
| 国 | 技術面でのサポート、リサイクル材の需要と供給をつなぐ仕組みづくり |
| 地方公共団体 | 地域でのリサイクル事業を支援する |
| 廃棄物処分業者 | より良いリサイクル技術の導入、リサイクル実績の公表 |
| 事業者 | ゴミの分別、リサイクルしやすい製品づくり、リサイクル材の活用 |
これらの取り組みを通じて、社会全体で資源循環を促進していくことが期待されています。
再資源化事業等高度化法の3つの認定制度の概要

この法律の目玉となるのが、3つの認定制度です。これらの制度では、国が認定した事業については廃棄物処理法の許可が不要になるなど、大きなメリットが用意されています。それぞれの制度について詳しく説明していきます。
①高度再資源化事業計画の認定(広域的なリサイクル事業)
この認定制度は、製造業者が必要とする質・量の再生材を確保するため、広域的な再資源化事業を対象としています。複数の地域をまたがって廃棄物を収集し、高品質な再資源化を実施する事業が対象となります。
具体例として、ペットボトルtoペットボトルの水平リサイクル、使用済みアルミ缶の電車車体材料への再生、廃プラスチックの高品質プラスチック製品への再生などが挙げられます。認定を受けると、廃棄物処理業許可の取得が不要になり、全国規模での事業展開が可能になります。
②高度分離・回収事業計画の認定(最新技術を活用した事業)
この認定制度は、廃棄物から価値のあるものを取り出したり、リサイクル材料を回収したりする事業を応援する制度です。最新技術を使ったリサイクルは、日本ではまだあまり行われていません。そこで成功例のノウハウを集めて、日本全国に同じような取り組みを広めることが目的となっています。
具体例として、太陽光パネルの100%リサイクル、風力発電ブレードの完全分解・再資源化、複合材料からの高精度分離技術などが挙げられます。認定を受けると、廃棄物処分業許可と施設設置許可の両方が不要となります。
③再資源化工程高度化計画の認定(既存施設の省エネ化支援)
この認定制度は、既に廃棄物処理施設を持っている事業者を対象として、温室効果ガスの排出量削減に資する設備の導入を推進するものです。既存の施設をより効率的で環境に優しいものにアップグレードすることが目的です。
具体例として、焼却炉の高効率設備への更新、再資源化工程のエネルギー削減設備導入、AI技術を活用した自動分別システム導入などが挙げられます。認定を受けることで、施設変更許可手続きの簡素化が図られます。
エアゾールバルブ製造のミタニが実践する循環型モノづくり
再資源化事業等高度化法により、製造業には高品質なリサイクル材の活用と、リサイクルしやすい製品設計がより強く求められるようになります。
私たち株式会社三谷バルブは、1956年の創業以来、日本で初めてエアゾールバルブの国産化を実現し、ヘアスプレーや殺虫剤スプレーなど身近な製品を通じて皆さまの生活を支えてきました。現在では「未来を照らすチカラ」をコーポレートメッセージに掲げ、環境に配慮した製品づくりに力を入れています。
社内では「ミクスチャーサイクル」という独自のシステムで、プラスチック部品の製造時に出るロス材料を再利用し、資源を最大限活用しています。
エアゾールバルブの製造でも、部品を一体型のプラスチックで作ることでリサイクルしやすい設計にするなど、製品を作る段階から環境のことを考えた取り組みを続けています。
創業から70年近く「世の中を変えるモノづくり企業」として歩んできた私たちの経験が、新しい法制度のもとでも持続可能な製造業を実現する力になっています。
ー 関連記事 ー