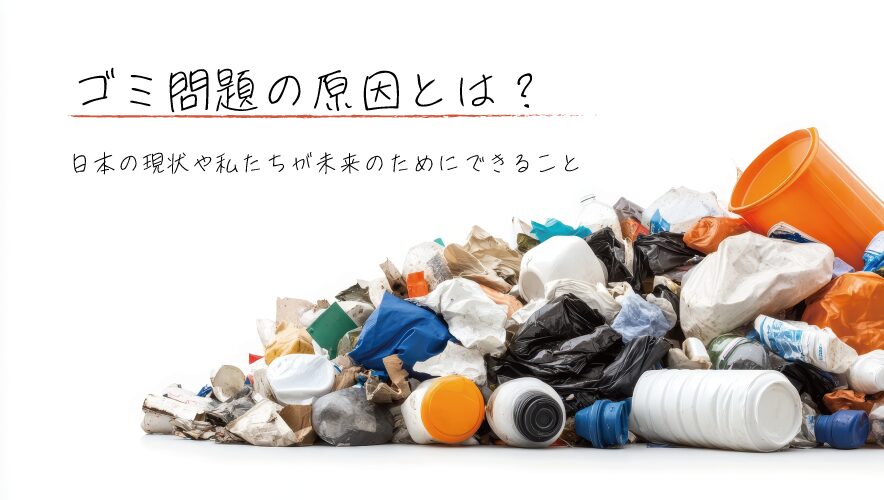身近なプラスチック製品から生まれる「廃プラ」について、正しく理解していますか?この記事では、廃プラの基本知識から最新のリサイクル技術まで、環境問題に関心のある方や事業者の方が知っておくべき重要なポイントを分かりやすく解説します。廃プラを適切に処理することで、どのように環境保護に貢献できるかを学びましょう。
廃プラ(廃プラスチック)とは?

私たちの生活に欠かせないプラスチック製品。その使用後に廃棄されたものや、製造過程で出た破片などを「廃プラスチック(廃プラ)」と呼びます。食品包装、容器、製品パーツなど多岐にわたって使われているプラスチックは、使い終わった後の処理方法が環境への大きな影響を与えているのが現状です。
廃プラは単なる「ゴミ」ではなく、適切な処理によって貴重な「資源」として生まれ変わる可能性を秘めています。
「廃プラ」と家庭の「プラスチックごみ」の違い
家庭で見かけるプラスチックと、工場や事業所で使われるプラスチックは、実は種類も用途も大きく異なります。家庭から出るプラスチックごみの代表例には、ペットボトル、食品トレイ、ビニール袋、調味料ボトルなどがあります。これらは日常生活で使う身近なものばかりです。
一方、工場や事業所から出る廃プラには、ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)、包装フィルム、PPバンド、スチロール、コンテナケースなどがあります。これらは製造業や流通業で大量に使用される業務用のプラスチック製品です。
お弁当の容器は家庭ごみですが、工場のプラスチックの切れ端は廃プラとして、全く違う処理が必要になります。
なぜ今「廃プラ問題」が世界で注目されるのか
廃プラ問題が世界的な注目を集める理由は、その深刻な環境への影響にあります。現在、年間約800万トンものプラスチックごみが海に流出しており、2018年時点で世界の海には合計1億5,000万トンの廃プラスチックが存在しています。
このペースで増加が続けば、2050年には海の魚よりプラスチックごみの量が多くなると予測されています。海洋生物の生態系破壊や人体への影響が懸念されており、まさに地球規模で解決すべき緊急課題となっているのです。
関連記事
ゴミ問題の原因、実は“3つの視点”で整理できます。
私たちの暮らしに何が起きているのか、一緒に見てみませんか?
参照:日本財団「2050年の海は魚よりもごみが多くなる?今すぐできる2つのアクション」
参照:WWFジャパン「海洋プラスチック問題について」
法律上の分類:産業廃棄物と一般廃棄物の違い

廃プラスチックは、どこから出たかによって、法律上の扱いが大きく2つに分かれます。「産業廃棄物」とは、事業活動(会社や工場など)から出る廃プラスチックのことです。「一般廃棄物」とは、家庭の日常生活から出るプラスチックごみのことを指します。重要なポイントは、同じプラスチック製品でも、排出元によって法律上の分類が変わることです。
具体的には、個人が家で飲んだペットボトルは「一般廃棄物」ですが、飲料メーカーの工場で製造中に不良品となったペットボトルは「産業廃棄物」です。産業廃棄物の廃プラスチックは、一般廃棄物として処理することはできません。
廃プラ処理の5つの流れ:排出~処分まで

廃プラスチックが適切に処理されるまでには、5つの重要なステップを経ていきます。各ステップで何が行われるのかを理解することで、廃プラ処理の全体像が見えてきます。特に「リサイクル」は、廃プラを貴重な資源として活用する重要な選択肢となっています。以下で詳しく見ていきましょう。
参照:公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会「リサイクルの流れ プラスチック容器包装(材料リサイクル)」
STEP1:分別・排出
すべての始まりは、家庭や事業所で正しく「分別」し、「排出」する(ゴミとして出す)ことです。家庭から出る「一般廃棄物」は自治体のルールに従って、事業所から出る「産業廃棄物」は法律で定められた基準に従って分別する必要があります。
この最初のステップでの正確な分別が、後のリサイクル率を大きく左右する非常に重要な工程となります。
STEP2:収集・運搬
分別・排出された廃プラスチックは、自治体の委託業者や産業廃棄物収集運搬の許可を持つ専門業者によって「収集」されます。収集された廃プラスチックは、次の「中間処理」が行われる施設(リサイクル工場)へと「運搬」されます。
この段階では、適切な許可を持つ業者による安全な運搬が求められ、廃プラスチックの品質を保ちながら処理施設まで届けることが重要になります。
STEP3:中間処理
廃プラスチックが収集された後、リサイクルに適した状態にするための工程が「中間処理」です。
ここでは主に以下の作業が行われます:
• 選別:手作業や機械によってリサイクルできるプラスチックとそうでないものを分ける。
• 破砕・圧縮:大きな廃プラスチックを細かく砕き、容積を減らす。
• 洗浄:汚れや異物を取り除き、リサイクル品質を高める。
STEP4:再生処理(リサイクル)
中間処理を経てリサイクル可能と判断された廃プラスチックが、新たな価値を持つ「資源」として生まれ変わる工程です。この段階で、大きく分けて3つのリサイクル方法(マテリアルリサイクル、ケミカルリサイクル、サーマルリサイクル)に分かれます。
それぞれの方法には特徴があり、プラスチックの種類や汚れ具合に応じて最適な手法が選ばれます。これらのリサイクル技術の詳しい内容については、次の章でじっくり解説します。
この段階で注目すべき事例が、製造業での新たな資源循環の取り組みです。三谷バルブでは、製造工程で発生するプラスチック端材や余剰資材を廃棄せず、有効に循環させる「ミクスチャーサイクル」という仕組みを実践しています。
ミクスチャーサイクルの特徴:
・年間約49トンの廃プラスチックを資源として再利用
・廃プラスチックを粉砕し、適切に選別・洗浄後、製造工程に再投入
・持続可能性と資源循環の両立を実現
このような取り組みは、製造業全体における廃プラスチック処理のあり方を変える可能性があります。
「廃プラスチック=ゴミ」という固定観念を覆し、資源循環の新しいモデルケースを提示する事例と言えるでしょう。
関連記事
STEP5:最終処分
様々な理由でリサイクルが困難だった廃プラスチックが、最終的にたどり着く場所です。日本の最終処分は、そのほとんどが「埋立処分」となっています。しかし、埋立地の確保が年々難しくなっていることや、環境への負荷といった課題があります。
プラスチックは自然分解しないため数百年間残り続けることから、だからこそステップ4のリサイクルの重要性がますます高まっているといえるでしょう。
廃プラを資源に変えるリサイクルの技術

廃プラスチックのリサイクル方法は、大きく分けて3つあります。
マテリアルリサイクル
廃プラスチックを溶かして新たなプラスチック製品として再資源化する方法
ケミカルリサイクル
廃プラスチックを化学的に分子レベルまで分解し、原料や燃料として再利用する方法
サーマルリサイクル
廃プラスチックを燃やした時に発生する熱をエネルギーとして回収し活用する方法
それぞれの詳しいメリット・デメリットについては、以下の表をご覧ください。
| リサイクル方法 | メリット(長所) | デメリット(短所) |
|---|---|---|
| マテリアルリサイクル | ・資源を「モノ」として循環させられる ・新品のプラスチックを作るよりCO2排出量が少ない | ・汚れや異物に弱く、品質が劣化しやすい(ダウンサイクル) ・リサイクルできる回数に限りがある |
| ケミカルリサイクル | ・新品同様の高品質なプラスチックや化学原料に戻せる ・不純物が混ざっていてもリサイクルしやすい | ・高度な技術が必要で、コストが高くなる傾向がある ・対応できる処理施設がまだ少ない |
| サーマルリサイクル | ・ゴミの量を大幅に減らすことができる ・発電や熱供給など、エネルギーとして有効活用できる | ・プラスチックという「資源」そのものは失われる ・燃焼時にCO2(二酸化炭素)が発生する |
これらのリサイクルによって、廃プラスチックは様々な製品に生まれ変わります。マテリアルリサイクルでは、衣類、包装用トレイ、コンテナ、ベンチ、フェンス、遊具、土木シートなどの製品になります。サーマルリサイクルでは、RPF(固形燃料)として石炭やコークスなどの化石燃料の代替として、製紙会社や鉄鋼会社などで広く利用されています。
日本では、サーマルリサイクルによる有効利用率が最も高くなっています。
参照:一般社団法人プラスチック循環利用協会「プラスチックリサイクルの基礎知識」
事業者が知っておくべき廃プラ処分の基礎知識

事業者が廃プラスチックを処分する際は、法律に基づいた適正な処理が必須となります。最も重要なのが「マニフェスト制度」の理解です。マニフェストは産業廃棄物が契約内容通りに適正処理されたかを確認するための管理伝票で、処理業者への引き渡し時に必ず交付しなければなりません。
また、処理業者選びでは許可証の確認が第一条件となります。廃棄物処理法に基づく適切な許可を持っているか、対応エリアと取り扱い可能な廃棄物の種類、環境への配慮と処理方法、実績と信頼性、料金体系の透明性をしっかりと確認しましょう。
不正な処理を行う業者への委託は、依頼した企業が5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方を科される可能性があるため、慎重な業者選択が不可欠です。
廃プラを「ゴミ」から「未来の資源」へ

私たちミタニは、すべての地球市民にとって最大のテーマである環境に配慮した製品づくりに積極的に取り組んできました。ミタニのミクスチャーサイクルのような革新的な技術によって生まれた製品は、持続可能な未来の街づくりに貢献しています。廃プラを「ゴミ」として終わらせるのではなく、「未来の資源」として循環させる取り組みが、より良い地球環境の実現につながるのです。
ミタニのミクスチャーサイクルについての記事はコチラをチェック。

– 関連記事 –