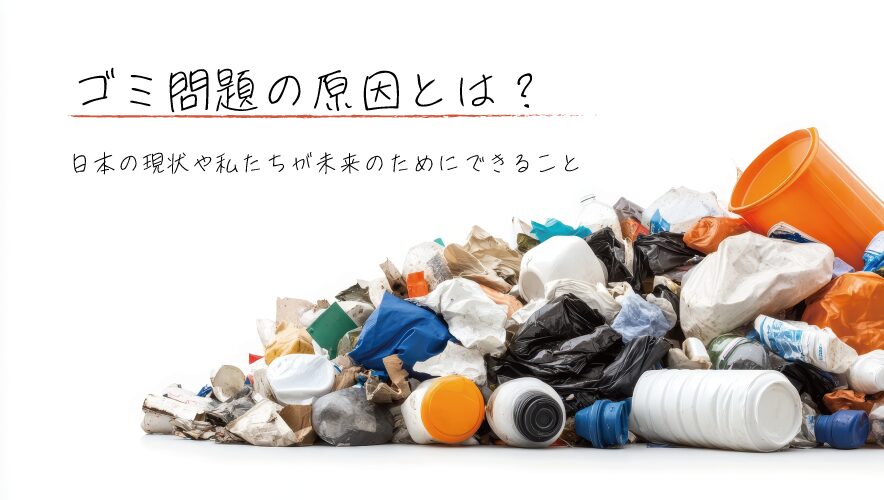「ゴミ問題ってよく聞くけど、結局なにが原因なの?」「自分にできることってあるのかな?」そんな風に感じていませんか?
この記事では、複雑に見えるゴミ問題の根本的な原因を、わかりやすく解説します。大量生産・大量消費の社会システムから、私たちのライフスタイルの変化、そして処理能力の限界まで、ゴミ問題の原因を3つの視点から紐解いていきます。まずは、私たちの身の回りで今、何が起きているのか一緒に見ていきましょう。
日本のゴミ問題の現状

日本のゴミ問題は、私たちが思っている以上に深刻な状況にあります。環境省の統計によると、日本人一人が一日に出すゴミの量は約851グラム。これは年間で約311キログラムという膨大な量になるのです。この数字を見ると、私たちがいかに多くのゴミを生み出しているかが分かるでしょう。
全国的には年間約4,000万トンものゴミが排出されており、これは10トントラック400万台分に相当します。処理費用も年間約2兆円という莫大な税金が投入されているのが現実です。以下では、ゴミの種類について詳しく見ていきましょう。
ゴミは2種類ある!家庭ごみと産業ごみ
世の中のゴミは、大きく分けて「一般廃棄物(家庭ごみなど)」と「産業廃棄物(工場などから出るごみ)」の2つに分類されます。
一般廃棄物は、私たちの家や学校、オフィスから出る生ゴミ、紙くず、プラスチック容器などが該当します。日常生活で見慣れた燃えるゴミや資源ゴミがこれに当たるでしょう。
一方、産業廃棄物は工場での製造過程や建設現場など、事業活動によって出る燃えがら、汚泥、廃プラスチック類などを指します。どちらも適切な処理が必要で、環境への影響を最小限に抑えるための取り組みが求められています。
なぜ?ゴミ問題が起こる3つの原因

ゴミ問題が深刻化している背景には、私たちの社会システムとライフスタイルの変化が大きく関わっています。これは、「作りすぎ」「捨てすぎ」「処理が追いつかない」という3つの構造的な問題が絡み合っているのです。
これらの原因を一つずつ詳しく見ていくことで、問題の本質が見えてくるでしょう。
原因1:モノを作りすぎ?「大量生産・大量消費」社会
私たちの社会は「新しいものを次々と作り、買い、そして捨てる」というサイクルが当たり前になっています。ファストファッションでは、シーズンごとに新しいデザインの洋服が店頭に並び、毎年新機能を搭載したスマートフォンが発売されているのが良い例でしょう。
「限定品」や「セール」といった言葉も、私たちの消費行動を刺激する仕組みの一つです。「今買わないと損をする」「この機会を逃したら手に入らない」という心理が働き、本当に必要かどうかを考える前に購入してしまうことがあります。
こうした社会の仕組みが、結果的に大量のゴミを生み出す原因となっているのです。
原因2:便利さの裏返し?私たちのライフスタイルの変化
大量生産・大量消費の社会システムは、私たちの日常生活にも大きな変化をもたらしました。核家族化や共働き世帯の増加により、「時短」や「手軽さ」を重視するライフスタイルが一般的になっています。
その結果、個包装の食品や冷凍食品、テイクアウトやデリバリーサービスの需要が高まりました。忙しい毎日の中で便利なサービスを利用することは決して悪いことではありませんが、これらのサービスには使い捨てプラスチック容器や包装材が多く使われています。
私たちが求める便利さの裏側で、知らず知らずのうちにゴミが増えてしまっているのが現状なのです。
原因3:リサイクルだけでは追いつかない「処理の限界」
「リサイクルを頑張っているのに、なぜゴミは減らないの?」という疑問を持つ方も多いでしょう。その答えは、日々大量に生み出されるゴミの量に対し、資源として再利用できる処理能力が追いついていないことにあります。
現実には、モノとして生まれ変わらせる処理には限界があるため、多くのゴミを燃やしてエネルギー回収する「サーマルリサイクル」に頼らざるを得ないのが現状です。つまり、リサイクル技術だけでは根本的な解決にはならず、そもそもゴミを減らす「リデュース」が最も重要だということが分かります。
この「処理の限界」という現実があるからこそ、次章で解説する影響が生まれてしまうのです。
関連記事:プラスチック、燃やすとどうなる?身近なゴミの行方と環境への影響
ゴミが増えるとどうなるの?地球と私たちへの3つの影響

ゴミの増加は単なる処理場不足の問題だけではありません。環境、健康、経済の3つの側面から、私たちの生活に深刻な影響を与えています。これらの影響は相互に関連し合い、放置すれば取り返しのつかない事態を招く可能性があるでしょう。具体的にどのような影響があるのか、一つずつ見ていきましょう。
環境への影響
ゴミの増加は地球環境に大きな負担をかけています。まず、ゴミの焼却時に発生するCO2が地球温暖化を加速させる要因となっています。大量のゴミを燃やすことで、年間数百万トンものCO2が大気中に放出されているのです。
海洋汚染も深刻な問題の一つです。海に流れ出たプラスチックゴミは簡単には自然分解されず、何百年もの間海を漂い続けます。これらが紫外線や波の力で細かく砕かれることで、5mm以下の「マイクロプラスチック」が生成されるのです。
さらに、不法投棄されたゴミから有害物質が染み出し、土や地下水を汚染する危険性も見過ごすことはできません。
私たちの健康への影響
ゴミ問題は環境だけでなく、私たちの健康にも直接的な影響を与えています。ゴミ焼却施設から排出されるダイオキシンなどの有害物質は、適切な処理がされていない場合、周辺住民の健康に影響を及ぼすリスクがあるでしょう。
前述したマイクロプラスチックは、海洋生物の体内に蓄積された後、食物連鎖を通じて私たちの食卓に届きます。魚介類を摂取することで、これらの微細な粒子が体内に取り込まれる可能性が指摘されているのです。
長期的な健康への影響はまだ完全には解明されていませんが、世界的な研究が進められている重要な課題となっています。
経済への影響
ゴミ処理には膨大な費用がかかっており、これらはすべて私たちの税金で賄われています。年間約2兆円という処理費用は、国民一人あたり約16,000円の負担に相当するのです。
この金額は決して小さくありません。もしゴミの量を減らすことができれば、その分を教育や医療、インフラ整備など、私たちの暮らしをより良くするために使うことができるでしょう。
ゴミ問題の解決は、環境保護だけでなく、税金の有効活用という経済的な観点からも重要な課題なのです。
明日からできる!ゴミ問題を解決する6つのアクション
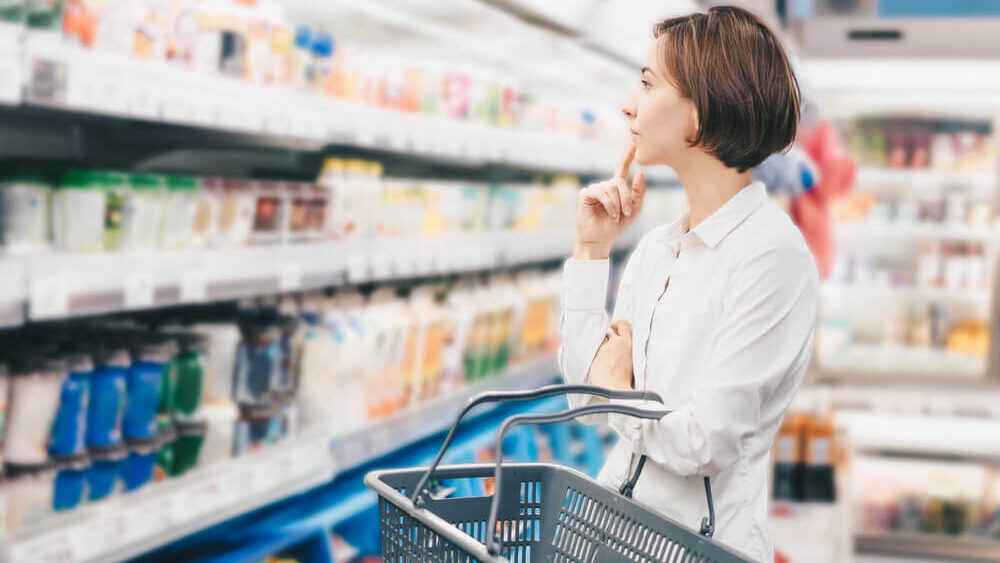
ゴミ問題は決して他人事ではありません。一人ひとりの行動が積み重なることで、大きな変化を生み出すことができます。難しく考える必要はなく、日常生活の中でできる小さな工夫から始めることが大切でしょう。以下では、レベル別に6つの具体的なアクションをご紹介します。自分のペースに合わせて、できることから始めてみてください。
関連記事:SDGsの身近な例を紹介!個人が日常生活でできる具体例や面白い取り組みも
Level 1:まずは定番!3Rを意識する

ゴミ削減の基本となるのが「3R」です。リデュース(Reduce:減らす)、リユース(Reuse:再利用)、リサイクル(Recycle:再生利用)の3つを指します。最も重要なのは「リデュース」で、そもそもゴミを出さないようにすることから始まります。
具体例としては、マイボトルやエコバッグを使うことでゴミを減らす(リデュース)、着なくなった服をフリマアプリで売る(リユース)、ペットボトルを正しく分別する(リサイクル)などがあります。この3つの順番を意識して、まずは「減らす」ことから取り組んでみましょう。
Level 2:買い物の仕方を変えてみる

日々の買い物での工夫が、ゴミ削減に大きな効果をもたらします。過剰包装の商品を避ける、量り売りを利用する、詰め替え用の製品を選ぶといった取り組みから始められるでしょう。
さらに重要なのは、「本当に必要か」を一度考えてから買うことです。特売やセールの誘惑に負けて衝動買いをしてしまうと、結局使わずに捨ててしまうことが多いもの。少し立ち止まって考える時間を作ることで、無駄な消費とゴミの発生を防ぐことができます。
Level 3:長く使える「良いモノ」を選ぶ

「安物買いの銭失い」ということわざがあるように、すぐに壊れてゴミになる製品ではなく、少し高くても丈夫で長持ちする製品を選ぶことが重要です。長期的に見れば、結果的にゴミを減らし、節約にもつながるでしょう。
修理して使える製品や、メーカーが長期保証を付けている製品を選ぶのも良い方法です。一つのモノを大切に長く使うことで、愛着も湧き、より豊かな暮らしを送ることができます。購入前には製品のレビューや耐久性を調べてから選ぶことをおすすめします。
Level 4:食品ロスをなくす

日本の家庭から出る「食品ロス」は年間233万トンにも上ります。これは事業系の231万トンをわずかに上回り、家庭での食品ロスの方が多いという衝撃的な事実が明らかになっています。まだ食べられる食品を捨ててしまうことは、もったいないという感情を超えて、深刻な環境問題なのです。
食品ロスをなくすための具体的な方法は、買いすぎない・使い切る・正しく保存する・手前どりを意識することです。冷蔵庫の中身を把握してから買い物に出かける、賞味期限の近い商品から購入する、余った食材は冷凍保存を活用するなど、日常の小さな工夫が大きな効果を生み出します。
ー 関連記事 ー
環境省:「我が国の食品ロスの発生量の推計値(令和5年度)の公表について」
Level 5: コンポストに挑戦する

生ゴミをゴミとして捨てるのではなく、微生物の力で分解させて「堆肥」に変える「コンポスト」は、家庭でできる究極のゴミ削減方法です。コンポストのメリットは多岐にわたります。
家庭ゴミの量を大幅に減らせる上、できた堆肥は家庭菜園や観葉植物の栄養になります。さらに、ゴミ焼却時のCO2排出量削減にも貢献できるでしょう。最近では室内でもできる小型のコンポスト容器も販売されているので、マンション住まいの方でも挑戦しやすくなっています。
Level 6:地域のクリーン活動に参加する

視点を「家の中」から「街」へと広げ、地域で行われている清掃活動への参加を検討してみましょう。「ボランティアって意識が高そう…」と感じる方もいるかもしれませんが、お散歩ついでにゴミを1つ拾う「プロギング」からでも始められます。
清掃活動に参加するメリットは、街がきれいになることはもちろん、同じ価値観を持つ仲間と出会える、問題の現状を肌で感じられることです。地域とのつながりも深まり、より良い住環境づくりにも貢献できるでしょう。
「ゴミにさせない」モノづくり。三谷バルブの挑戦
ゴミ問題の解決には、個人の取り組みだけでなく、企業側の責任ある製造も欠かせません。私たち一人ひとりができる3Rやコンポストなどのアクションと併せて、企業が行う革新的な取り組みも重要な役割を果たしています。
三谷バルブでは、独自の「ミクスチャーサイクル」技術を通じて、製造過程で発生する端材や余剰資材を再利用し、新品同等の品質を保ちながら資源の循環利用を実現しています。この技術により年間約49トンもの廃棄樹脂を有効活用し、CO2削減とコストダウンを同時に達成しているのです。
持続可能な社会の実現には、消費者と企業が一体となって取り組むことが不可欠でしょう。私たちが環境に配慮した製品を選び、企業がそれに応える技術開発を続けることで、「ゴミにさせない」未来を作ることができます。
三谷バルブの製品について詳しくは知りたい方は商品ページをご覧ください。