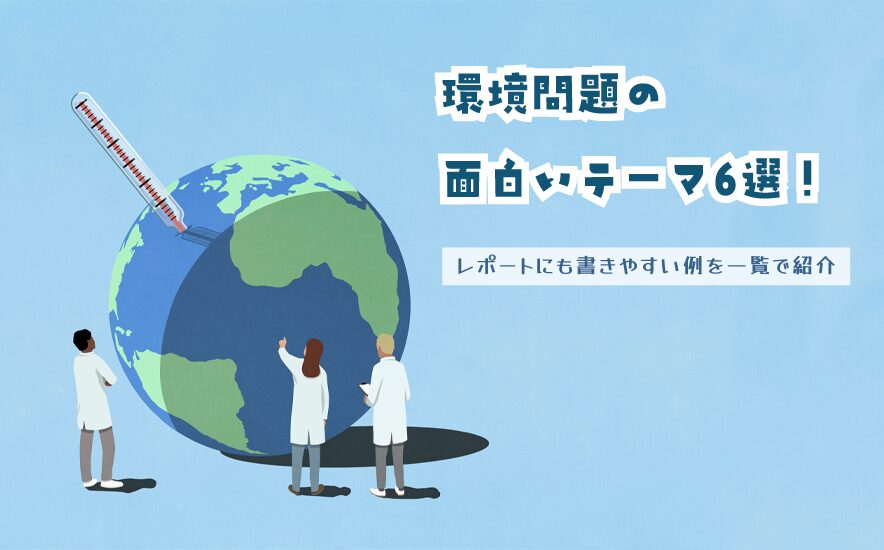環境問題について勉強したり、レポートを書いたりする時、「どんなテーマを選べばいいかわからない」と悩む学生は多いでしょう。この記事では、身近で興味深い環境問題のテーマを6個紹介します。スマートフォンの製造からファッションに至るまで、意外な角度から環境問題を学べるテーマを選びました。自由研究やレポート作成に役立つテーマ選びのコツも説明するので、環境問題について調べたい学生におすすめです。
環境問題とは
環境問題とは、人間の活動が原因で起こった地球環境の変化によって生まれる様々な問題のことです。地球温暖化や海洋汚染、森林破壊、水質汚染、土壌汚染などが代表的な例として挙げられます。
これらの問題が注目されるようになったきっかけは、18世紀後半の産業革命です。経済が発展する中で石炭や石油といった化石燃料が大量に使われるようになり、私たちの生活は便利になりました。
しかしその一方で、大気や海、川、土壌に有害物質が広まり、自然環境が悪化してしまいました。環境問題は自然環境を悪化・破壊させて生態系に大きな影響を与え、私たち人間にとっても深刻な脅威となっています。
レポートで書きやすい環境問題の面白いテーマ6選

学生がレポートで取り組みやすい環境問題のテーマを選ぶ際は、身近で興味深く、調べやすいものを選ぶことが重要です。難しすぎる問題よりも、読み手が「そうなんだ!」と驚けるような意外性のあるテーマを選ぶと、より魅力的なレポートになります。
以下では、そうした観点から厳選した6のテーマを紹介していきます。
スマホの製造が環境に与える影響:1台作るのに何トンの水が必要?
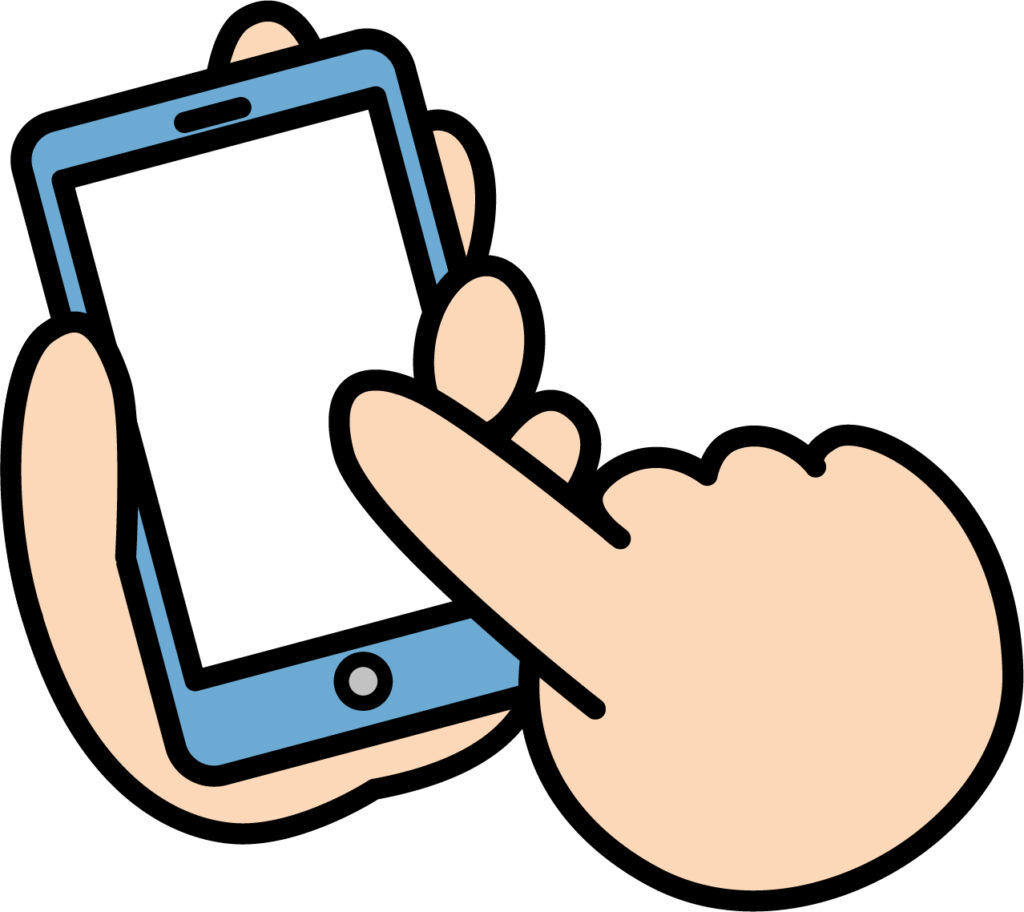
私たちが毎日使っているスマートフォンは、製造過程で大量の環境負荷を生み出しています。スマートフォン1台の製造には910リットルもの水が必要で、これは大人が3年かけて飲む水の量に相当します。
世界で約45億台のスマートフォンが使用されており、これらから年間1億4600万トンの二酸化炭素が排出されています。特に注目すべきは、新品スマートフォンを1年間使用した時の温室効果ガス排出量平均85kgのうち、実際の使用による排出はわずか5%に過ぎないことです。
残りの95%は製造過程で排出されており、原材料の採掘から部品の組み立てまで、様々な工程で大量のエネルギーが消費されています。
参照:厚生労働省「健康のため水を飲もう講座」
参照:厚生労働省「〈参考〉 水 1 基本的事項 2 水の必要量を算定するための根拠」
ファストファッションの真実:1着作るのに浴槽11杯分の水が消える

手頃な価格でトレンドを取り入れた洋服が手に入るファストファッションですが、その製造には驚くほど多くの水が使われています。1枚のTシャツを作るのに約2,700リットルの水が必要で、これは家庭用浴槽約11杯分に相当します。
ファッション業界全体では世界のCO2排出量の約10%を占めており、これは国際航空便と海運業を合わせた排出量より多い数値です。さらに深刻なのは廃棄の問題で、製造された衣類の85%が毎年ごみとして処分され、リサイクル率は1%以下という状況です。
世界の繊維生産量は過去20年で2倍近く増加し、日本では年間の新規供給量に対し廃棄される量が約6割に達しています。
牛のゲップが地球温暖化の原因?:畜産業の意外な影響
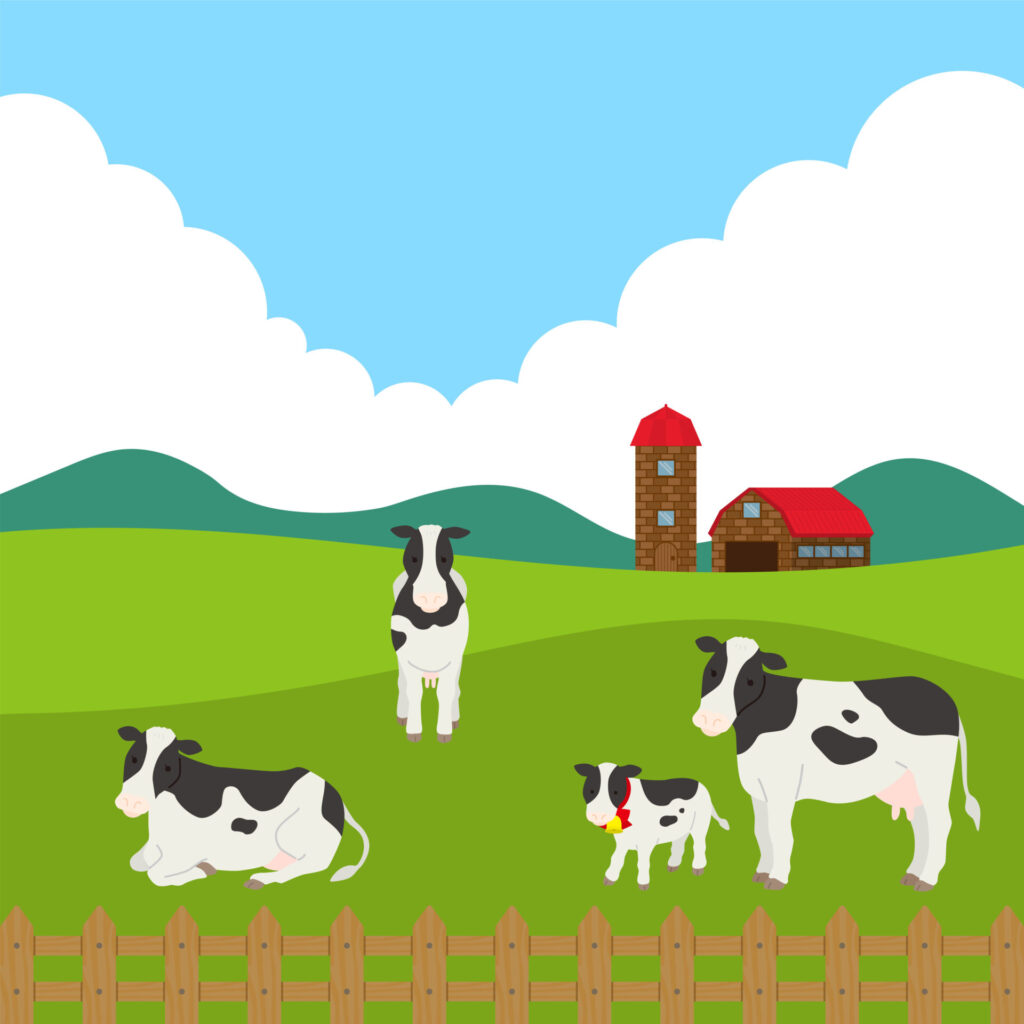
意外に思われるかもしれませんが、牛のゲップは地球温暖化の重要な原因の一つです。牛は反すう動物として、第一胃に住む微生物によって草を消化しますが、この過程でメタンガスが発生します。
育てられている牛1頭は年間約61.3kgのメタンを出し、牛肉1kgの生産に0.462kgのメタンが排出されます。メタンの温室効果は二酸化炭素の25倍もあります。さらに、飼料生産や排せつ物処理なども含めると、牛肉生産全体では1kgあたり二酸化炭素換算で約20kgの温室効果ガスが発生します。
私たち日本人は年間約6.2kgの牛肉を食べているため、一人当たり年間124kgの二酸化炭素が牛肉消費により発生している計算になります。
参照:一般社団法人 全国肉用牛振興基金協会「牛のゲップが地球温暖化の原因と聞きましたが本当ですか?」
化粧品に潜む環境破壊:マイクロビーズが海を汚染する仕組み

洗顔料や歯磨き粉に含まれるマイクロビーズという微細なプラスチック粒子が、深刻な海洋汚染を引き起こしています。マイクロビーズは0.1mm以下と非常に小さく、目に見えないほど細かい粒子です。
これらの粒子は使用後に排水として流され、通常の排水処理施設では除去できないため、川や海に流れ着いてしまいます。マイクロビーズは自然分解されることがなく、数百年以上にわたって環境中に残り続けます。
海洋生物がこれらをエサと間違って誤食し、食物連鎖を通じて最終的に人間の体内にも取り込まれる可能性が懸念されています。このため、アメリカやEUなど多くの国でマイクロビーズの使用規制が始まっており、日本でも業界による自主規制が進められています。
年間25億トンの食品ロス:世界の飢餓人口を超える量の廃棄

世界では年間約25億トンもの食品が廃棄されており、これは生産された全食品の約40%にあたります。一方で、世界では約7億1300万人から7億5700万人(凡そ11人に1人)が飢餓状態にあり、食の不平等が深刻な問題となっています。
食品廃棄は環境にも大きな負荷をかけています。世界で年間に排出される二酸化炭素のうち10%を食品廃棄物が占めており、これはアメリカとヨーロッパで自動車が1年間に排出する量のほぼ2倍に相当します。
日本では年間464万トンの食品ロスが発生しており、国民一人当たりでは年間約37kg、一日約103グラム(茶碗約1杯分のご飯に相当)の食品が無駄になっています。食品ロスを減らすことは、飢餓問題の解決と地球温暖化対策の両方に貢献する重要な取り組みです。
参照:農林水産省「食品ロスの現状を知る」
参照:日本財団ジャーナル「世界で捨てられる食べ物の量、年間25億トン。食品ロスを減らすためにできること」
服をシェアする時代:レンタルファッションが変える消費のかたち

「服は買うもの」という従来の考え方が「必要な時に借りるもの」へと変わりつつあります。ファッションレンタルサービスは、環境負荷の削減と新しい消費スタイルの両立を実現する画期的なサービスです。
環境省の実証事業によると、ファッションレンタルサービスは通常の販売モデルと比較して、CO2排出量を19%削減、廃棄物排出量を27%削減できることが確認されています。これは衣服の過剰生産・廃棄を抑制し、一着の服を複数の人でシェアすることで実現されています。
レンタル時の配送による環境負荷を考慮しても、製造段階での環境負荷削減効果の方が大きく、サーキュラーファッション(循環型ファッション)の取り組みとして持続可能な社会の実現に貢献しています。
参照:環境省「第3節 モノは所有から共有へ(シェアリング・エコノミー)
自分に合った環境問題のテーマ選びのポイント

効果的な環境問題テーマを選択することは、魅力的なレポートや研究を作成する上で極めて重要です。単に「環境に良いテーマ」を選ぶのではなく、自分自身が興味を持って取り組め、読み手にとっても面白い内容にできるテーマを見つけることが大切です。
以下では、テーマ選びの際に考慮すべき4つの重要なポイントについて詳しく解説していきます。
1.自分が興味のある分野を見つける
レポート作成において最も重要な要素の一つが、個人の興味関心とテーマの一致です。自分が興味を持てないテーマでは、調査や執筆の過程でモチベーションを維持することが困難になってしまいます。
まずは普段の生活を振り返り、どのような分野に関心があるかを整理してみましょう。例えば、ファッションに興味があるならファストファッション問題、食べ物が好きなら食品ロス問題といったように、自分の趣味や関心事から環境問題へのアプローチを見つけることができます。
興味のある分野から環境問題を捉えることで、より深い理解と独自の視点を得ることが可能になります。
2.調べやすさをチェックする
情報収集の難易度は、レポート作成の成功を大きく左右する要因です。どんなに興味深いテーマでも、信頼できる情報や具体的なデータが入手困難では、質の高いレポートを作成することはできません。
調べやすいテーマの特徴として、政府機関や国際機関が公式データを公表している、研究論文や専門書が豊富にある、最近注目されている話題で関連記事が多いなどが挙げられます。テーマを決める前に、図書館やインターネットで基本的な情報収集を行い、十分な資料が存在するかを確認しておきましょう。
また、専門用語が多すぎて理解が困難でないか、データの入手に時間がかかりすぎないかも事前にチェックしておくことが重要です。
3.他の人と違う視点を探す
同じ環境問題を扱っても、独自の視点や切り口があることで、オリジナリティのあるレポートに仕上げることができます。誰もが知っている一般的な内容だけでは、読み手の興味を引くことは難しいでしょう。
独自の視点を見つけるためには、問題を多角的に捉えることが大切です。例えば、地球温暖化について書く場合、単に原因と対策を述べるのではなく、「なぜ牛のゲップが問題になるのか」「スマートフォンの製造がどう関係するのか」といった意外な角度からアプローチすることで、読み手の関心を引くことができます。
また、身近な体験や地域の事例を盛り込むことで、より親しみやすく興味深い内容にすることも可能です。
4.資料やデータが十分あるか確認する
説得力のあるレポートを作成するためには、信頼できる資料やデータの裏付けが不可欠です。感想や推測だけでは学術的なレポートとして成立しないため、客観的な事実やデータに基づいた論証が必要です。
信頼できる資料の見分け方として、官公庁や研究機関、国際機関が発表したデータを優先的に使用することが挙げられます。環境省、農林水産省、国連などの公式資料は特に信頼性が高いと言えるでしょう。また、学術論文や専門書、新聞記事なども有効な情報源となります。
一方で、個人のブログやSNSの情報は信頼性に欠ける場合があるため注意が必要です。データが不足している場合は、テーマの範囲を調整したり、別の切り口を検討したりすることも大切になってきます。
私たちにできる環境問題の身近な取り組み

環境問題は国や企業だけでなく、私たち一人ひとりの行動によって改善できる問題でもあります。日常生活の中で少し意識を変えるだけで、地球環境の保護に貢献することができます。
個人レベルでできる取り組みとして、自家用車の代わりに公共交通機関を利用する、マイバッグを持参してレジ袋の使用を減らす、ごみの分別を徹底してリサイクルを促進する、節水や節電を心がけるなどがあります。
また、詰め替え製品の利用、食べ切れる量だけの食材購入、再生可能エネルギーを使った電力会社への切り替えなども効果的な取り組みです。これらの小さな行動の積み重ねが、大きな環境改善につながっていきます。
三谷バルブは企業として環境問題に取り組んでいます
株式会社三谷バルブでは、製造業としての責任を果たすため、積極的に環境問題に取り組んでいます。持続可能な社会の実現に向けて、様々な環境配慮活動を推進しています。
具体的な取り組みとして、2024年8月にはISCC PLUS認証を取得し、持続可能な製品供給への取り組みを国際的に証明しました。また、白河工場と茨城工場に太陽光発電システムを導入し、再生可能エネルギーの活用を進めています。
白河工場では年間260トンのCO2削減を見込んでおり、これは杉の木約1万8600本が1年間に吸収するCO2量に相当します。このように企業レベルでの環境配慮活動も、地球環境保護に大きく貢献しています。
– 関連記事 –